スポンサードリンク
障害者をまるごと検索
障害者を詳しく調べる
障害者でお困りなら、ご確認してみてください。
お近くのバリアフリー(介護)リフォーム業者から
無料見積もりをお取り寄せして比較できます。
忙しいあなたにも手間なく、
ご自分の目線で、信頼の出来る工務店や
リフォーム業者をお選びいただき、
安心のリフォーム工事を行っていただければと思います。
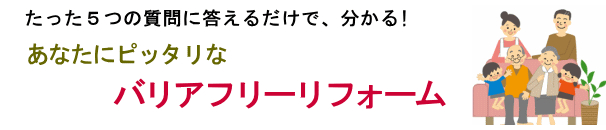
障害者の関連情報
障害者とは?
障害者
障害者または障碍者(しょうがいしゃ、challenged)とは、なんらかの機能の不全(障害)があるために、日常生活や社会生活に制約を受ける人のこと。定義上は、身体障害者、知的障害者、精神障害者を含むが、日常語としては身体障害者のみを指す場合がある。
障害の医療モデルとアプローチについてはリハビリテーション#障害の分類と対策を参照のこと。
障害者基本法では、第二条において、障がい者を以下のように定義している。
身体障者については、身体障害者福祉法第四条において次のよう害に定義している。
「別表」として6項目を掲げ、「視力障害」「聴覚または平衡機能の障害」「音声機能、言語機能、咀嚼機能の障害」「肢体不自由」「重篤な心臓、腎臓、呼吸器機能の障害」というべきものをそれぞれに定義している。
障害者自立支援法
題名=障害者自立支援法
番号=平成17年法律第123号
通称=なし
効力=現行法
種類=社会保障法
内容=障害者の自立に向けた支援
関連=身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、児童福祉法
障害者自立支援法(しょうがいしゃじりつしえんほう)とは、「障害者 障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができる」ようにすることを目的とする日本の法律である。
従来の制度と比較して、障害に対する継続的な医療費の自己負担比率が、5%から10%に倍増した。狙いは、少子高齢化社会に向け、従来の支援費制度に代わり、障害者に費用の原則1割負担を求め、障害者の福祉サービスを一元化し、保護から自立に向けた支援にある。
障害者スポーツ
障害者スポーツ(しょうがいしゃスポーツ)は、身体障害や知的障害などの障害を持つ人が行うスポーツのこと。既存のスポーツを障害者の要求に応じて修正したものが多い。「(障害者に)合わせたスポーツ」の意でアダプテッド・スポーツ (adapted sports) ともいう。しかしながら、全部が健常者のスポーツの修正版ではなく、障害者のために考案された独自のスポーツもいくつか存在する。
障害者選手のためのスポーツは、障害の種類によってろう者・身体障害者・知的障害者の3グループに大きく分けられる。それぞれに個別の歴史があり、組織・競技大会・取り組み方もまた異なる。
1986年、国際知的障害者スポーツ連盟 (INAS-FID) が設立された。この組織は知的障害者選手のエリート競技を支援することを目的としており、「スポーツ・フォー・オール みんなのスポーツ ("sport for all") 」のアプローチを取るスペシャルオリンピックスとは対照的である。一時はパラリンピックに知的障害者選手が出場していたが、2000年の夏季パラリンピックにおいて複数の健常者が知的障害クラスに出場したという不正行為が発覚し、それ以降は INAS-FID の選手はパラリンピックの正式競技から排除されている。現在、パラリンピックに復帰するための活動が進行中である。
障害者割引サービス (携帯電話)
障害者割引サービス(しょうがいしゃわりびき-)は、携帯電話料金の割引サービスの一つ。NTTドコモではハーティ割引(ふれあい割引)、Au (携帯電話) auではスマイルハート割引、ソフトバンクモバイルではハートフレンド割引と称される。
障害者を対象に基本料金・通話料・通信料等が割引になるサービス。適応対象となるのは、
身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
といったいわゆる障害者手帳の交付を受けている人に限られる。しかし、最近は各社料金プランの複雑化、低料金化が進み、割引サービスの恩恵が薄くなり、場合によっては割高になってしまう場合がある(そのためか、2008年以降同サービスの改定も開始されている)。
なお、このサービスは1名義あたり1回線までと決められており、年間割引サービスなどのように1名義で複数契約することはできない。
障害者基本法
障害者基本法(しょうがいしゃきほんほう)は、日本における障害者のための施策に関する基本的な事項を定めた法律である。
2004年(平成16年)6月4日、障害者基本法の一部を改正する法律が公布(一部施行)され、法律の目的、障害者の定義、基本的理念などに関わる部分を含む、大幅な改正が行われた。本改正によって、「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」ことが基本的理念として明記された。
以下に、2004年改正法のうち、法律の目的、障害者の定義、基本的理念などに関わる第1条〜第3条を抄出する(太字が改正箇所)。なお、改正第2条の施行は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(2005年(平成17年)4月1日)より、改正第3条の施行は2007年(平成19年)4月1日よりとなっている。
障害者割引サービス
障害者割引サービス(しょうがいしゃわりびき-)は、携帯電話料金の割引サービスの一つ。NTTドコモグループではハーティ割引(ふれあい割引)、Au (携帯電話) auではスマイルハート割引、ボーダフォンではプライオリティサポートと称される。
障害者を対象に基本料金・通話料・通信料等が割引になるサービス。適応対象となるのは、
身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
といった俗にいう「障害者手帳」の交付を受けている人に限られる。
このサービスの利用には上記の「障害者手帳」の提示と申し込みが必要だが、定額料金等はかからない。だがこのサービスに加入すると年間割引サービスや継続割引サービスの対象外になる。
障害者差別
障害者差別とは、リハビリテーション#障害の医療モデル 障害が外見的なものであろうとなかろうと、それによって人権や生存権が損なわれ、その人の人生にとって後遺症となりうるような経験を障害者本人の意図とは無関係に強いられるもの、具体的には障害者に対する暴力や名誉毀損、不妊手術の強要などから、障害を理由として社会参加等が制限されるような制度的或は運用上の差別及び排除・具体的には隔離から欠格 欠格条項等による就学・就職差別、介護放棄などをいう。
スウェーデンでは、1906年に「優性」を理由とする不妊手術が行なわれたのを皮切りに、1915年には、優生学的理由から「精神遅滞、精神病、てんかん」者の結婚の規制が行なわれた。
障害者福祉
障害者福祉(しょうがいしゃふくし)は、身体、知的発達、精神に障害を持つ人々に対して自立を支援する福祉サービスを指し、児童も含むことが多い。広義では障害年金などの所得保障・医療保障、また雇用・住宅施策も含む。日本では第二次世界大戦後、身体に障害を持った傷痍軍人等への「対策的な」施策として身体障害者福祉が発足したが、現在では、障害を持っていても健常者と同様に自立して暮らすノーマライゼーションの考え方や、社会的統合(インテグレーション)を理念とするようになった。
障害者には身体障害者、知的障害者、精神障害者の3つの種類があり、誕生のときからの先天性障害、乳幼幼児期の病気による障害、成人になってからの障害、事故による障害など原因は様々であり、重複障害の場合もある。
障害者職業生活相談員
障害者職業生活相談員(しょうがいしゃしょくぎょうせいかつそうだんいん)とは、障害者職業生活相談員資格認定講習を修了した者。
障害者を5人以上雇用する事業所において、「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、障害者の職業生活全般にわたる相談・指導を行う障害者職業生活相談員を選任することとなっている。
常用の障害者を5人以上雇用している事業所の従業員で、職業生活相談員として選任が予定される者
次の者は資格者として認められ、受講の必要はない
職業訓練大学校の福祉工学科修了者
大学・高等専門学校卒業後、1年以上障害者の生活相談・指導を経験した者
障害者手帳
障害者手帳(しょうがいしゃてちょう)とは、下記のものをいう。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳といった、障害を有する人に対して発行される手帳の総称。
精神障害者に対して発行される手帳の名称。正式名称は精神障害者保健福祉手帳。表紙には「障害者手帳」とのみ表示され、表紙を見ただけでは障害の種類は分からないようになっている。精神障害者を参照。
「障害者手帳」と称する場合、あらゆる障害者の手帳を指すこともあるし、精神障害者の手帳のみを指すこともある。
したがって、手帳の制度について知識がない者に対し、「障害者手帳」という用語を用いる場合、混乱を招くこともある。
障害者または障碍者(しょうがいしゃ、challenged)とは、なんらかの機能の不全(障害)があるために、日常生活や社会生活に制約を受ける人のこと。定義上は、身体障害者、知的障害者、精神障害者を含むが、日常語としては身体障害者のみを指す場合がある。
障害の医療モデルとアプローチについてはリハビリテーション#障害の分類と対策を参照のこと。
障害者基本法では、第二条において、障がい者を以下のように定義している。
身体障者については、身体障害者福祉法第四条において次のよう害に定義している。
「別表」として6項目を掲げ、「視力障害」「聴覚または平衡機能の障害」「音声機能、言語機能、咀嚼機能の障害」「肢体不自由」「重篤な心臓、腎臓、呼吸器機能の障害」というべきものをそれぞれに定義している。
障害者自立支援法
題名=障害者自立支援法
番号=平成17年法律第123号
通称=なし
効力=現行法
種類=社会保障法
内容=障害者の自立に向けた支援
関連=身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、児童福祉法
障害者自立支援法(しょうがいしゃじりつしえんほう)とは、「障害者 障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができる」ようにすることを目的とする日本の法律である。
従来の制度と比較して、障害に対する継続的な医療費の自己負担比率が、5%から10%に倍増した。狙いは、少子高齢化社会に向け、従来の支援費制度に代わり、障害者に費用の原則1割負担を求め、障害者の福祉サービスを一元化し、保護から自立に向けた支援にある。
障害者スポーツ
障害者スポーツ(しょうがいしゃスポーツ)は、身体障害や知的障害などの障害を持つ人が行うスポーツのこと。既存のスポーツを障害者の要求に応じて修正したものが多い。「(障害者に)合わせたスポーツ」の意でアダプテッド・スポーツ (adapted sports) ともいう。しかしながら、全部が健常者のスポーツの修正版ではなく、障害者のために考案された独自のスポーツもいくつか存在する。
障害者選手のためのスポーツは、障害の種類によってろう者・身体障害者・知的障害者の3グループに大きく分けられる。それぞれに個別の歴史があり、組織・競技大会・取り組み方もまた異なる。
1986年、国際知的障害者スポーツ連盟 (INAS-FID) が設立された。この組織は知的障害者選手のエリート競技を支援することを目的としており、「スポーツ・フォー・オール みんなのスポーツ ("sport for all") 」のアプローチを取るスペシャルオリンピックスとは対照的である。一時はパラリンピックに知的障害者選手が出場していたが、2000年の夏季パラリンピックにおいて複数の健常者が知的障害クラスに出場したという不正行為が発覚し、それ以降は INAS-FID の選手はパラリンピックの正式競技から排除されている。現在、パラリンピックに復帰するための活動が進行中である。
障害者割引サービス (携帯電話)
障害者割引サービス(しょうがいしゃわりびき-)は、携帯電話料金の割引サービスの一つ。NTTドコモではハーティ割引(ふれあい割引)、Au (携帯電話) auではスマイルハート割引、ソフトバンクモバイルではハートフレンド割引と称される。
障害者を対象に基本料金・通話料・通信料等が割引になるサービス。適応対象となるのは、
身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
といったいわゆる障害者手帳の交付を受けている人に限られる。しかし、最近は各社料金プランの複雑化、低料金化が進み、割引サービスの恩恵が薄くなり、場合によっては割高になってしまう場合がある(そのためか、2008年以降同サービスの改定も開始されている)。
なお、このサービスは1名義あたり1回線までと決められており、年間割引サービスなどのように1名義で複数契約することはできない。
障害者基本法
障害者基本法(しょうがいしゃきほんほう)は、日本における障害者のための施策に関する基本的な事項を定めた法律である。
2004年(平成16年)6月4日、障害者基本法の一部を改正する法律が公布(一部施行)され、法律の目的、障害者の定義、基本的理念などに関わる部分を含む、大幅な改正が行われた。本改正によって、「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」ことが基本的理念として明記された。
以下に、2004年改正法のうち、法律の目的、障害者の定義、基本的理念などに関わる第1条〜第3条を抄出する(太字が改正箇所)。なお、改正第2条の施行は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(2005年(平成17年)4月1日)より、改正第3条の施行は2007年(平成19年)4月1日よりとなっている。
障害者割引サービス
障害者割引サービス(しょうがいしゃわりびき-)は、携帯電話料金の割引サービスの一つ。NTTドコモグループではハーティ割引(ふれあい割引)、Au (携帯電話) auではスマイルハート割引、ボーダフォンではプライオリティサポートと称される。
障害者を対象に基本料金・通話料・通信料等が割引になるサービス。適応対象となるのは、
身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
といった俗にいう「障害者手帳」の交付を受けている人に限られる。
このサービスの利用には上記の「障害者手帳」の提示と申し込みが必要だが、定額料金等はかからない。だがこのサービスに加入すると年間割引サービスや継続割引サービスの対象外になる。
障害者差別
障害者差別とは、リハビリテーション#障害の医療モデル 障害が外見的なものであろうとなかろうと、それによって人権や生存権が損なわれ、その人の人生にとって後遺症となりうるような経験を障害者本人の意図とは無関係に強いられるもの、具体的には障害者に対する暴力や名誉毀損、不妊手術の強要などから、障害を理由として社会参加等が制限されるような制度的或は運用上の差別及び排除・具体的には隔離から欠格 欠格条項等による就学・就職差別、介護放棄などをいう。
スウェーデンでは、1906年に「優性」を理由とする不妊手術が行なわれたのを皮切りに、1915年には、優生学的理由から「精神遅滞、精神病、てんかん」者の結婚の規制が行なわれた。
障害者福祉
障害者福祉(しょうがいしゃふくし)は、身体、知的発達、精神に障害を持つ人々に対して自立を支援する福祉サービスを指し、児童も含むことが多い。広義では障害年金などの所得保障・医療保障、また雇用・住宅施策も含む。日本では第二次世界大戦後、身体に障害を持った傷痍軍人等への「対策的な」施策として身体障害者福祉が発足したが、現在では、障害を持っていても健常者と同様に自立して暮らすノーマライゼーションの考え方や、社会的統合(インテグレーション)を理念とするようになった。
障害者には身体障害者、知的障害者、精神障害者の3つの種類があり、誕生のときからの先天性障害、乳幼幼児期の病気による障害、成人になってからの障害、事故による障害など原因は様々であり、重複障害の場合もある。
障害者職業生活相談員
障害者職業生活相談員(しょうがいしゃしょくぎょうせいかつそうだんいん)とは、障害者職業生活相談員資格認定講習を修了した者。
障害者を5人以上雇用する事業所において、「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、障害者の職業生活全般にわたる相談・指導を行う障害者職業生活相談員を選任することとなっている。
常用の障害者を5人以上雇用している事業所の従業員で、職業生活相談員として選任が予定される者
次の者は資格者として認められ、受講の必要はない
職業訓練大学校の福祉工学科修了者
大学・高等専門学校卒業後、1年以上障害者の生活相談・指導を経験した者
障害者手帳
障害者手帳(しょうがいしゃてちょう)とは、下記のものをいう。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳といった、障害を有する人に対して発行される手帳の総称。
精神障害者に対して発行される手帳の名称。正式名称は精神障害者保健福祉手帳。表紙には「障害者手帳」とのみ表示され、表紙を見ただけでは障害の種類は分からないようになっている。精神障害者を参照。
「障害者手帳」と称する場合、あらゆる障害者の手帳を指すこともあるし、精神障害者の手帳のみを指すこともある。
したがって、手帳の制度について知識がない者に対し、「障害者手帳」という用語を用いる場合、混乱を招くこともある。