スポンサードリンク
高齢者をまるごと検索
高齢者を詳しく調べる
高齢者でお困りなら、ご確認してみてください。
お近くのバリアフリー(介護)リフォーム業者から
無料見積もりをお取り寄せして比較できます。
忙しいあなたにも手間なく、
ご自分の目線で、信頼の出来る工務店や
リフォーム業者をお選びいただき、
安心のリフォーム工事を行っていただければと思います。
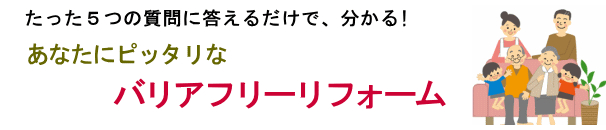
高齢者の関連情報
高齢者とは?
高齢者
高齢の線引きは曖昧且つ主観的な部分があり、判断は容易ではない。定年退職者もしくは老齢年金給付対象以上の人を言うことも考えられる。国連の世界保健機関 (WHO) の定義では、65歳以上の人のことを高齢者としている。65 ? 74歳までを前期高齢者、75歳以上を後期高齢者、85歳以上を末期高齢者という。因みに、人口の年齢構造では、0 ? 14歳までを年少人口、15 ? 64歳までを生産年齢人口、65歳以上を高齢人口という。
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(略称:高年齢者雇用安定法)における「高年齢者」とは、55歳以上の者を言う高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和46年労働省令第24号)。
高年齢者雇用安定法における「高年齢者等」とは、「高年齢者」、および55歳未満の「中高年齢者」(45歳以上の者)である求職者、および55歳未満の「中高年齢失業者等」(45歳以上65歳未満の失業者その他就職が特に困難な失業者、具体的には身体障害 身体障害者、刑法等の規定により保護観察に付された者等で、その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があった者
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
題名=高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
通称 バリアフリー新法
番号=平成18年6月21日法律第91号
効力=現行法
種類=行政法
内容=高齢者、障害者等の移動等の円滑化を目的とする法律
関連=都市計画法、建築基準法
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(こうれいしゃ、しょうがいしゃとうのいどうとうのえんかつかのそくしんにかんするほうりつ、平成18年6月21日法律第91号)は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性にかんがみ、公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物の構造及び設備を改善するための措置、一定の地区における旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設の一体的な整備を推進するための措置その他の措置を講ずることにより、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする法律(第1条)。
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律
題名=高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律
通称=ハートビル法
番号=平成6年法律第44号
効力=現行法
種類=法律
内容=高齢者や身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進等
関連=高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律 交通バリアフリー法
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(こうれいしゃ、しんたいしょうがいしゃとうがえんかつにりようできるとくていけんちくぶつのけんちくのそくしんにかんするほうりつ;1994年 平成6年6月29日法律第44号)とは、以下に示す目的で制定された日本の法律である。ハートビル法と通称される。最終改正は平成16年(2004年)6月18日。
高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律
題名=高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律
通称=交通バリアフリー法
番号=平成12年法律第68号
効力=現行法
種類=法律
内容=高齢者や身体障害者等が円滑に利用できる公共交通機関の促進等
関連=高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律 ハートビル法
高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(こうれいしゃ、しんたいしょうがいしゃとうのこうつうきかんをりようしたいどうのえんかつかのそくしんにかんするほうりつ;2000年 平成12年5月17日法律第68号)通称、「交通バリアフリー法」と呼ばれる。
高齢者の医療の確保に関する法律
題名=高齢者の医療の確保に関する法律
通称=
番号=昭和57年8月17日法律第80号
効力=現行法
種類=法律
内容=後期高齢者医療制度、特定健康診査等
関連=各種健康保険関係の法律など
高齢者の医療の確保に関する法律(こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつ)は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的として制定された法律である。2007年3月31日まで題号が「老人保健法」だったが、後期高齢者医療制度の発足にあわせ2008年4月1日に現在の題名に変更された。
高齢者虐待
高齢者虐待(こうれいしゃぎゃくたい, Elder abuse)とは、家庭内や施設内での高齢者に対する虐待行為である。
この行為では、高齢者の基本的人権を侵害・蹂躙し、心や身体に深い傷を負わせるようなもので、次のような種類がある。
身体的な虐待
: 殴る、蹴る、つねるなどで、裂傷や打撲などの跡を残すことがある。本人の意に反し手足を縛る身体的拘束もある。
性的な虐待
: 性的な暴力(高齢者夫婦間でのドメスティックバイオレンス-DVも含む)。
心理的な虐待
: 脅迫や侮辱などの言葉による暴力、恫喝、侮蔑。
ネグレクト(介護や世話の放棄)
: 生活に必要な介護の拒否、意図的な怠慢、必要な医療や食事、衣類や暖房の提供をしない、病気の放置など、生活上の不合理な制限、戸外への締め出し。
高齢者福祉
高齢者福祉(こうれいしゃふくし)とは、社会福祉制度の一分野で、特に高齢者を対象とするサービスのことを指し、老人福祉とも呼ばれる。広義では高齢者の所得保障や医療保障などを含む。日本では、人口の高齢化が世界に類を見ないスピードで上昇し、高齢化率14%以上の高齢社会から、数年後21%以上の超高齢社会の域に達する見込みであり、サービス受給者は増加の一途をたどっている。
高齢化はサービスを必要とする人口の増加と、サービスの担い手であり税・保険料負担の大きい若年世代の人口の相対的減少を意味し、増加する一途の費用をどこに求めるかが課題となっている。
2000年度から介護保険制度が発足した、これにより介護サービスの充実のため、老人介護を公的社会保険で行うこととなった。
高齢者マーク
『高齢運転者標識』より : 高齢運転者標識(こうれいうんてんしゃひょうしき)とは、道路交通法に基づく標識の一つ。水 水滴もしくは葉 葉っぱのように見える形状をしており、左がオレンジ色、右が黄色に塗り分けられ、初心者マークに比して紅葉のように見えることから、一般的には紅葉マーク(もみじマーク)や、シルバーマーク、高齢者マークの通称で呼ばれるが、俗称として落ち葉マークや枯れ葉マークと呼ばれることもある。
高齢者の自動車事故が多発していたことから、道路交通法の改正により、初心者マークに倣って、1997年(平成9年)に75歳以上を対象に導入された。
2002年(平成14年)には、対象年齢を75歳以上から70歳以上に引き下げる改正が行われた。
高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
題名=高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
番号=平成17年11月9日法律第124号
通称=高齢者虐待防止法
効力=現行法
種類=行政法
内容=高齢者の虐待の防止及び高齢者の養護者の支援
関連=老人福祉法
高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(こうれいしゃのぎゃくたいのぼうし、こうれいしゃのようごしゃにたいするしえんとうにかんするほうりつ)、通称高齢者虐待防止法(こうれいしゃぎゃくたいぼうしほう)は、高齢者の虐待の防止に関する国の責務、虐待を受けた高齢者の保護措置、養護者の高齢者虐待防止のための支援措置を定めた日本の法律である。
高齢者虐待防止法
『高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律』より : 題名=高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
番号=平成17年11月9日法律第124号
通称=高齢者虐待防止法
効力=現行法
種類=行政法
内容=高齢者の虐待の防止及び高齢者の養護者の支援
関連=老人福祉法
高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(こうれいしゃのぎゃくたいのぼうし、こうれいしゃのようごしゃにたいするしえんとうにかんするほうりつ)、通称高齢者虐待防止法(こうれいしゃぎゃくたいぼうしほう)は、高齢者の虐待の防止に関する国の責務、虐待を受けた高齢者の保護措置、養護者の高齢者虐待防止のための支援措置を定めた日本の法律である。
高齢の線引きは曖昧且つ主観的な部分があり、判断は容易ではない。定年退職者もしくは老齢年金給付対象以上の人を言うことも考えられる。国連の世界保健機関 (WHO) の定義では、65歳以上の人のことを高齢者としている。65 ? 74歳までを前期高齢者、75歳以上を後期高齢者、85歳以上を末期高齢者という。因みに、人口の年齢構造では、0 ? 14歳までを年少人口、15 ? 64歳までを生産年齢人口、65歳以上を高齢人口という。
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(略称:高年齢者雇用安定法)における「高年齢者」とは、55歳以上の者を言う高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和46年労働省令第24号)。
高年齢者雇用安定法における「高年齢者等」とは、「高年齢者」、および55歳未満の「中高年齢者」(45歳以上の者)である求職者、および55歳未満の「中高年齢失業者等」(45歳以上65歳未満の失業者その他就職が特に困難な失業者、具体的には身体障害 身体障害者、刑法等の規定により保護観察に付された者等で、その者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があった者
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
題名=高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
通称 バリアフリー新法
番号=平成18年6月21日法律第91号
効力=現行法
種類=行政法
内容=高齢者、障害者等の移動等の円滑化を目的とする法律
関連=都市計画法、建築基準法
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(こうれいしゃ、しょうがいしゃとうのいどうとうのえんかつかのそくしんにかんするほうりつ、平成18年6月21日法律第91号)は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性にかんがみ、公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物の構造及び設備を改善するための措置、一定の地区における旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設の一体的な整備を推進するための措置その他の措置を講ずることにより、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする法律(第1条)。
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律
題名=高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律
通称=ハートビル法
番号=平成6年法律第44号
効力=現行法
種類=法律
内容=高齢者や身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進等
関連=高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律 交通バリアフリー法
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(こうれいしゃ、しんたいしょうがいしゃとうがえんかつにりようできるとくていけんちくぶつのけんちくのそくしんにかんするほうりつ;1994年 平成6年6月29日法律第44号)とは、以下に示す目的で制定された日本の法律である。ハートビル法と通称される。最終改正は平成16年(2004年)6月18日。
高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律
題名=高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律
通称=交通バリアフリー法
番号=平成12年法律第68号
効力=現行法
種類=法律
内容=高齢者や身体障害者等が円滑に利用できる公共交通機関の促進等
関連=高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律 ハートビル法
高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(こうれいしゃ、しんたいしょうがいしゃとうのこうつうきかんをりようしたいどうのえんかつかのそくしんにかんするほうりつ;2000年 平成12年5月17日法律第68号)通称、「交通バリアフリー法」と呼ばれる。
高齢者の医療の確保に関する法律
題名=高齢者の医療の確保に関する法律
通称=
番号=昭和57年8月17日法律第80号
効力=現行法
種類=法律
内容=後期高齢者医療制度、特定健康診査等
関連=各種健康保険関係の法律など
高齢者の医療の確保に関する法律(こうれいしゃのいりょうのかくほにかんするほうりつ)は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的として制定された法律である。2007年3月31日まで題号が「老人保健法」だったが、後期高齢者医療制度の発足にあわせ2008年4月1日に現在の題名に変更された。
高齢者虐待
高齢者虐待(こうれいしゃぎゃくたい, Elder abuse)とは、家庭内や施設内での高齢者に対する虐待行為である。
この行為では、高齢者の基本的人権を侵害・蹂躙し、心や身体に深い傷を負わせるようなもので、次のような種類がある。
身体的な虐待
: 殴る、蹴る、つねるなどで、裂傷や打撲などの跡を残すことがある。本人の意に反し手足を縛る身体的拘束もある。
性的な虐待
: 性的な暴力(高齢者夫婦間でのドメスティックバイオレンス-DVも含む)。
心理的な虐待
: 脅迫や侮辱などの言葉による暴力、恫喝、侮蔑。
ネグレクト(介護や世話の放棄)
: 生活に必要な介護の拒否、意図的な怠慢、必要な医療や食事、衣類や暖房の提供をしない、病気の放置など、生活上の不合理な制限、戸外への締め出し。
高齢者福祉
高齢者福祉(こうれいしゃふくし)とは、社会福祉制度の一分野で、特に高齢者を対象とするサービスのことを指し、老人福祉とも呼ばれる。広義では高齢者の所得保障や医療保障などを含む。日本では、人口の高齢化が世界に類を見ないスピードで上昇し、高齢化率14%以上の高齢社会から、数年後21%以上の超高齢社会の域に達する見込みであり、サービス受給者は増加の一途をたどっている。
高齢化はサービスを必要とする人口の増加と、サービスの担い手であり税・保険料負担の大きい若年世代の人口の相対的減少を意味し、増加する一途の費用をどこに求めるかが課題となっている。
2000年度から介護保険制度が発足した、これにより介護サービスの充実のため、老人介護を公的社会保険で行うこととなった。
高齢者マーク
『高齢運転者標識』より : 高齢運転者標識(こうれいうんてんしゃひょうしき)とは、道路交通法に基づく標識の一つ。水 水滴もしくは葉 葉っぱのように見える形状をしており、左がオレンジ色、右が黄色に塗り分けられ、初心者マークに比して紅葉のように見えることから、一般的には紅葉マーク(もみじマーク)や、シルバーマーク、高齢者マークの通称で呼ばれるが、俗称として落ち葉マークや枯れ葉マークと呼ばれることもある。
高齢者の自動車事故が多発していたことから、道路交通法の改正により、初心者マークに倣って、1997年(平成9年)に75歳以上を対象に導入された。
2002年(平成14年)には、対象年齢を75歳以上から70歳以上に引き下げる改正が行われた。
高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
題名=高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
番号=平成17年11月9日法律第124号
通称=高齢者虐待防止法
効力=現行法
種類=行政法
内容=高齢者の虐待の防止及び高齢者の養護者の支援
関連=老人福祉法
高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(こうれいしゃのぎゃくたいのぼうし、こうれいしゃのようごしゃにたいするしえんとうにかんするほうりつ)、通称高齢者虐待防止法(こうれいしゃぎゃくたいぼうしほう)は、高齢者の虐待の防止に関する国の責務、虐待を受けた高齢者の保護措置、養護者の高齢者虐待防止のための支援措置を定めた日本の法律である。
高齢者虐待防止法
『高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律』より : 題名=高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
番号=平成17年11月9日法律第124号
通称=高齢者虐待防止法
効力=現行法
種類=行政法
内容=高齢者の虐待の防止及び高齢者の養護者の支援
関連=老人福祉法
高齢者の虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(こうれいしゃのぎゃくたいのぼうし、こうれいしゃのようごしゃにたいするしえんとうにかんするほうりつ)、通称高齢者虐待防止法(こうれいしゃぎゃくたいぼうしほう)は、高齢者の虐待の防止に関する国の責務、虐待を受けた高齢者の保護措置、養護者の高齢者虐待防止のための支援措置を定めた日本の法律である。