スポンサードリンク
障害をまるごと検索
障害を詳しく調べる
障害でお困りなら、ご確認してみてください。
お近くのバリアフリー(介護)リフォーム業者から
無料見積もりをお取り寄せして比較できます。
忙しいあなたにも手間なく、
ご自分の目線で、信頼の出来る工務店や
リフォーム業者をお選びいただき、
安心のリフォーム工事を行っていただければと思います。
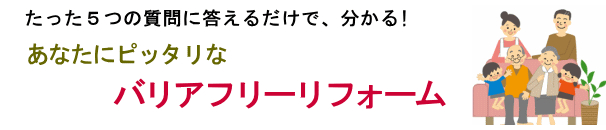
障害の関連情報
障害とは?
障害
障害(しょうがい。”しょうげ”の慣用読みから)とは、
本来「障碍」「障礙」と書いて、ものごとの達成や進行のさまたげとなること。また、さまたげとなるもののこと。※なお、「礙」は「碍」の字体#正字体 本字であるが、煩雑を避けるため、以下「碍」で統一する。
本来「障害」と書いて、なんらかの障碍によって発生するダメージやトラブルのこと。
本来「障害」とも「障碍」とも書いて、医学上の「障害」。 明治時代に作られた用法。
医学用語から派生したものとして、いわゆる「障害者」というときの「障害」。近年では「障がい」と書くことが多い。
別読語として、仏教では「悟りの妨げになるもの」を指して「障礙 (仏教) 障礙」(しょうげ)と呼ぶ。
障害を扱った作品の一覧
障害を扱った作品の一覧(しょうがいをあつかったさくひんのいちらん)は、視覚障害者 視覚障害・聴覚障害者 聴覚障害・肢体不自由・発達障害といった障害、またそれらの障害を持つ人々をテーマにした作品の一覧である。
清作の妻(吉田絃二郎)
田園交響楽(アンドレ・ジッド)
ベルナのしっぽ(郡司ななえ)
暗いところで待ち合わせ(乙一,2002年 幻冬舎)
仮面舞踏会 (小説) 仮面舞踏会(横溝正史)- 色覚異常を扱った作品
悪魔の設計図(横溝正史)
- 連続殺人が盲目娘の遺産相続人に忍び寄る。
月の盾(岩田洋季)- 色覚異常を扱った作品
春琴抄(谷崎潤一郎 1933 中央公論)
- 病気で盲目となる大店(おおだな)の娘の春琴と丁稚の佐助の愛情物語。
藏 蔵(宮尾登美子 1993 毎日新聞社)
障害者
障害者または障碍者(しょうがいしゃ、challenged)とは、なんらかの機能の不全(障害)があるために、日常生活や社会生活に制約を受ける人のこと。定義上は、身体障害者、知的障害者、精神障害者を含むが、日常語としては身体障害者のみを指す場合がある。
障害の医療モデルとアプローチについてはリハビリテーション#障害の分類と対策を参照のこと。
障害者基本法では、第二条において、障がい者を以下のように定義している。
身体障者については、身体障害者福祉法第四条において次のよう害に定義している。
「別表」として6項目を掲げ、「視力障害」「聴覚または平衡機能の障害」「音声機能、言語機能、咀嚼機能の障害」「肢体不自由」「重篤な心臓、腎臓、呼吸器機能の障害」というべきものをそれぞれに定義している。
障害児
『障害者』より : 障害者(しょうがいしゃ)・障害児(しょうがいじ)とは、なんらかの発達上の障害、行動、感情のコントロールを含めて身体的な機能不全、生活上の行動の規制を伴うような障害を持っている人をいう。「障害者」という用字についてはさまざまな議論がある(後述の「#表記 表記」を参照)。
障害の分類とアプローチについてはリハビリテーションを参照。
戦前の日本では、公的な障害者施策は、ほとんど行われることがなかった。
もっとも、古来の日本の神道では、何か特別な能力を持った対象として、障害者を畏敬したという。そして、障害者の中には、神職など祭儀を司る役割を担ってきた者もいたという。また、江戸時代には、幼少期に視力を喪失しながら、国学者として、その能力を存分に発揮した実在の人物(塙保己一)も存在する。これらの歴史的な記録から、障害者に対して差別的な見方がされるようになったのは、近代以降であるとする見解がある。
障害者自立支援法
題名=障害者自立支援法
番号=平成17年法律第123号
通称=なし
効力=現行法
種類=社会保障法
内容=障害者の自立に向けた支援
関連=身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、児童福祉法
障害者自立支援法(しょうがいしゃじりつしえんほう)とは、「障害者 障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができる」ようにすることを目的とする日本の法律である。
従来の制度と比較して、障害に対する継続的な医療費の自己負担比率が、5%から10%に倍増した。狙いは、少子高齢化社会に向け、従来の支援費制度に代わり、障害者に費用の原則1割負担を求め、障害者の福祉サービスを一元化し、保護から自立に向けた支援にある。
障害者スポーツ
障害者スポーツ(しょうがいしゃスポーツ)は、身体障害や知的障害などの障害を持つ人が行うスポーツのこと。既存のスポーツを障害者の要求に応じて修正したものが多い。「(障害者に)合わせたスポーツ」の意でアダプテッド・スポーツ (adapted sports) ともいう。しかしながら、全部が健常者のスポーツの修正版ではなく、障害者のために考案された独自のスポーツもいくつか存在する。
障害者選手のためのスポーツは、障害の種類によってろう者・身体障害者・知的障害者の3グループに大きく分けられる。それぞれに個別の歴史があり、組織・競技大会・取り組み方もまた異なる。
1986年、国際知的障害者スポーツ連盟 (INAS-FID) が設立された。この組織は知的障害者選手のエリート競技を支援することを目的としており、「スポーツ・フォー・オール みんなのスポーツ ("sport for all") 」のアプローチを取るスペシャルオリンピックスとは対照的である。一時はパラリンピックに知的障害者選手が出場していたが、2000年の夏季パラリンピックにおいて複数の健常者が知的障害クラスに出場したという不正行為が発覚し、それ以降は INAS-FID の選手はパラリンピックの正式競技から排除されている。現在、パラリンピックに復帰するための活動が進行中である。
障害物競走
障害物競走(しょうがいぶつきょうそう)は運動会で行われる競技のひとつ。コース中に設けられたさまざまな障害を超えながらゴールに到達する早さを競う競技。
障害物競走のコースにはさまざまな障害物が設置されている。競技者はその障害を順番に超えながらゴールを目指す。障害の多くは物理的には無視して避けて進むことが可能なように設置されているが、そのような行為は障害物競走の存在意義をなくしてしまうため、ずるい行為であるとして許されない。徒競走やリレー走 リレーなどは純粋に走る速さを競う競技であるが、障害物競走は必ずしも走る速さだけで勝つことはできない。そのため、運動の苦手な児童・生徒も運動会に積極的に参加できるようにするために有効な競技である。だが、その分競技というよりもレクリエーションとしての面が強調され、運動会の競技の中ではやや地味な存在である。
障害者割引サービス (携帯電話)
障害者割引サービス(しょうがいしゃわりびき-)は、携帯電話料金の割引サービスの一つ。NTTドコモではハーティ割引(ふれあい割引)、Au (携帯電話) auではスマイルハート割引、ソフトバンクモバイルではハートフレンド割引と称される。
障害者を対象に基本料金・通話料・通信料等が割引になるサービス。適応対象となるのは、
身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
といったいわゆる障害者手帳の交付を受けている人に限られる。しかし、最近は各社料金プランの複雑化、低料金化が進み、割引サービスの恩恵が薄くなり、場合によっては割高になってしまう場合がある(そのためか、2008年以降同サービスの改定も開始されている)。
なお、このサービスは1名義あたり1回線までと決められており、年間割引サービスなどのように1名義で複数契約することはできない。
障害児教育
『特別支援教育』より : 特別支援教育(とくべつしえんきょういく)というのは、日本の障害児教育の新しい呼称。2001年の春から文部科学省は、旧来の特殊教育という言い方に代わって、この呼称を使用している。発達支援教育(はったつしえんきょういく)、特別発達支援教育という言い方もする。文部科学省では、英語表記はspecial support educationという表現を充てている。2006年6月、「学校教育法の一部改訂に関する法案」が国会で承認され、2007年4月より、盲学校、聾学校、養護学校は、すべて障害の種類を越えて、特別支援学校という呼称に統一され、教員免許の制度もこれに合わせて変更されることになった。従来の障害児の種類分けに加えて、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、高機能自閉症などの子どもたちにも充分な配慮と支援をしていくことになった。
障害競走
障害競走(しょうがいきょうそう)とは、コース上に生垣、竹柵、土塁、水濠などを設けて、そこを飛越しながら速さを争う競馬の競走である。障害の飛越の際の落馬の危険性があるが、平地競走にはない魅力がある。
日本ではジャンプレースとも呼ばれる。日本においては居留地競馬の時代から障害競走が行われており、1862年(文久2年)の『The Japan Herald』掲載の競走番組表に施行予定競走のひとつとして記載されているものが障害競走に関する最古の記録である。
現在障害競走を開催している競馬場は東京競馬場、中山競馬場、京都競馬場、阪神競馬場、福島競馬場、新潟競馬場、中京競馬場、小倉競馬場の8つ。この内、福島・新潟・中京は障害専用のコースを持たないため(但し、福島・中京は襷コースがあるが新潟はない)、芝コースに障害物を設置して行われる。札幌競馬場や函館競馬場では行なわれない(戦前には行われていた)。また、福島・新潟・中京・小倉の裏開催(第三場としての開催時)にも行われない。かつては川崎競馬場などの地方競馬でも障害競走が施行されていたが現在は行われておらず(但し、競馬法 競馬法施行令第17条の4により施行することはできる)、名古屋競馬場など一部の地方競馬場には障害コースの名残が見られる。したがって、アングロアラブ アラブの障害競走は日本に現存しない。
障害(しょうがい。”しょうげ”の慣用読みから)とは、
本来「障碍」「障礙」と書いて、ものごとの達成や進行のさまたげとなること。また、さまたげとなるもののこと。※なお、「礙」は「碍」の字体#正字体 本字であるが、煩雑を避けるため、以下「碍」で統一する。
本来「障害」と書いて、なんらかの障碍によって発生するダメージやトラブルのこと。
本来「障害」とも「障碍」とも書いて、医学上の「障害」。 明治時代に作られた用法。
医学用語から派生したものとして、いわゆる「障害者」というときの「障害」。近年では「障がい」と書くことが多い。
別読語として、仏教では「悟りの妨げになるもの」を指して「障礙 (仏教) 障礙」(しょうげ)と呼ぶ。
障害を扱った作品の一覧
障害を扱った作品の一覧(しょうがいをあつかったさくひんのいちらん)は、視覚障害者 視覚障害・聴覚障害者 聴覚障害・肢体不自由・発達障害といった障害、またそれらの障害を持つ人々をテーマにした作品の一覧である。
清作の妻(吉田絃二郎)
田園交響楽(アンドレ・ジッド)
ベルナのしっぽ(郡司ななえ)
暗いところで待ち合わせ(乙一,2002年 幻冬舎)
仮面舞踏会 (小説) 仮面舞踏会(横溝正史)- 色覚異常を扱った作品
悪魔の設計図(横溝正史)
- 連続殺人が盲目娘の遺産相続人に忍び寄る。
月の盾(岩田洋季)- 色覚異常を扱った作品
春琴抄(谷崎潤一郎 1933 中央公論)
- 病気で盲目となる大店(おおだな)の娘の春琴と丁稚の佐助の愛情物語。
藏 蔵(宮尾登美子 1993 毎日新聞社)
障害者
障害者または障碍者(しょうがいしゃ、challenged)とは、なんらかの機能の不全(障害)があるために、日常生活や社会生活に制約を受ける人のこと。定義上は、身体障害者、知的障害者、精神障害者を含むが、日常語としては身体障害者のみを指す場合がある。
障害の医療モデルとアプローチについてはリハビリテーション#障害の分類と対策を参照のこと。
障害者基本法では、第二条において、障がい者を以下のように定義している。
身体障者については、身体障害者福祉法第四条において次のよう害に定義している。
「別表」として6項目を掲げ、「視力障害」「聴覚または平衡機能の障害」「音声機能、言語機能、咀嚼機能の障害」「肢体不自由」「重篤な心臓、腎臓、呼吸器機能の障害」というべきものをそれぞれに定義している。
障害児
『障害者』より : 障害者(しょうがいしゃ)・障害児(しょうがいじ)とは、なんらかの発達上の障害、行動、感情のコントロールを含めて身体的な機能不全、生活上の行動の規制を伴うような障害を持っている人をいう。「障害者」という用字についてはさまざまな議論がある(後述の「#表記 表記」を参照)。
障害の分類とアプローチについてはリハビリテーションを参照。
戦前の日本では、公的な障害者施策は、ほとんど行われることがなかった。
もっとも、古来の日本の神道では、何か特別な能力を持った対象として、障害者を畏敬したという。そして、障害者の中には、神職など祭儀を司る役割を担ってきた者もいたという。また、江戸時代には、幼少期に視力を喪失しながら、国学者として、その能力を存分に発揮した実在の人物(塙保己一)も存在する。これらの歴史的な記録から、障害者に対して差別的な見方がされるようになったのは、近代以降であるとする見解がある。
障害者自立支援法
題名=障害者自立支援法
番号=平成17年法律第123号
通称=なし
効力=現行法
種類=社会保障法
内容=障害者の自立に向けた支援
関連=身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、児童福祉法
障害者自立支援法(しょうがいしゃじりつしえんほう)とは、「障害者 障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができる」ようにすることを目的とする日本の法律である。
従来の制度と比較して、障害に対する継続的な医療費の自己負担比率が、5%から10%に倍増した。狙いは、少子高齢化社会に向け、従来の支援費制度に代わり、障害者に費用の原則1割負担を求め、障害者の福祉サービスを一元化し、保護から自立に向けた支援にある。
障害者スポーツ
障害者スポーツ(しょうがいしゃスポーツ)は、身体障害や知的障害などの障害を持つ人が行うスポーツのこと。既存のスポーツを障害者の要求に応じて修正したものが多い。「(障害者に)合わせたスポーツ」の意でアダプテッド・スポーツ (adapted sports) ともいう。しかしながら、全部が健常者のスポーツの修正版ではなく、障害者のために考案された独自のスポーツもいくつか存在する。
障害者選手のためのスポーツは、障害の種類によってろう者・身体障害者・知的障害者の3グループに大きく分けられる。それぞれに個別の歴史があり、組織・競技大会・取り組み方もまた異なる。
1986年、国際知的障害者スポーツ連盟 (INAS-FID) が設立された。この組織は知的障害者選手のエリート競技を支援することを目的としており、「スポーツ・フォー・オール みんなのスポーツ ("sport for all") 」のアプローチを取るスペシャルオリンピックスとは対照的である。一時はパラリンピックに知的障害者選手が出場していたが、2000年の夏季パラリンピックにおいて複数の健常者が知的障害クラスに出場したという不正行為が発覚し、それ以降は INAS-FID の選手はパラリンピックの正式競技から排除されている。現在、パラリンピックに復帰するための活動が進行中である。
障害物競走
障害物競走(しょうがいぶつきょうそう)は運動会で行われる競技のひとつ。コース中に設けられたさまざまな障害を超えながらゴールに到達する早さを競う競技。
障害物競走のコースにはさまざまな障害物が設置されている。競技者はその障害を順番に超えながらゴールを目指す。障害の多くは物理的には無視して避けて進むことが可能なように設置されているが、そのような行為は障害物競走の存在意義をなくしてしまうため、ずるい行為であるとして許されない。徒競走やリレー走 リレーなどは純粋に走る速さを競う競技であるが、障害物競走は必ずしも走る速さだけで勝つことはできない。そのため、運動の苦手な児童・生徒も運動会に積極的に参加できるようにするために有効な競技である。だが、その分競技というよりもレクリエーションとしての面が強調され、運動会の競技の中ではやや地味な存在である。
障害者割引サービス (携帯電話)
障害者割引サービス(しょうがいしゃわりびき-)は、携帯電話料金の割引サービスの一つ。NTTドコモではハーティ割引(ふれあい割引)、Au (携帯電話) auではスマイルハート割引、ソフトバンクモバイルではハートフレンド割引と称される。
障害者を対象に基本料金・通話料・通信料等が割引になるサービス。適応対象となるのは、
身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
といったいわゆる障害者手帳の交付を受けている人に限られる。しかし、最近は各社料金プランの複雑化、低料金化が進み、割引サービスの恩恵が薄くなり、場合によっては割高になってしまう場合がある(そのためか、2008年以降同サービスの改定も開始されている)。
なお、このサービスは1名義あたり1回線までと決められており、年間割引サービスなどのように1名義で複数契約することはできない。
障害児教育
『特別支援教育』より : 特別支援教育(とくべつしえんきょういく)というのは、日本の障害児教育の新しい呼称。2001年の春から文部科学省は、旧来の特殊教育という言い方に代わって、この呼称を使用している。発達支援教育(はったつしえんきょういく)、特別発達支援教育という言い方もする。文部科学省では、英語表記はspecial support educationという表現を充てている。2006年6月、「学校教育法の一部改訂に関する法案」が国会で承認され、2007年4月より、盲学校、聾学校、養護学校は、すべて障害の種類を越えて、特別支援学校という呼称に統一され、教員免許の制度もこれに合わせて変更されることになった。従来の障害児の種類分けに加えて、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、高機能自閉症などの子どもたちにも充分な配慮と支援をしていくことになった。
障害競走
障害競走(しょうがいきょうそう)とは、コース上に生垣、竹柵、土塁、水濠などを設けて、そこを飛越しながら速さを争う競馬の競走である。障害の飛越の際の落馬の危険性があるが、平地競走にはない魅力がある。
日本ではジャンプレースとも呼ばれる。日本においては居留地競馬の時代から障害競走が行われており、1862年(文久2年)の『The Japan Herald』掲載の競走番組表に施行予定競走のひとつとして記載されているものが障害競走に関する最古の記録である。
現在障害競走を開催している競馬場は東京競馬場、中山競馬場、京都競馬場、阪神競馬場、福島競馬場、新潟競馬場、中京競馬場、小倉競馬場の8つ。この内、福島・新潟・中京は障害専用のコースを持たないため(但し、福島・中京は襷コースがあるが新潟はない)、芝コースに障害物を設置して行われる。札幌競馬場や函館競馬場では行なわれない(戦前には行われていた)。また、福島・新潟・中京・小倉の裏開催(第三場としての開催時)にも行われない。かつては川崎競馬場などの地方競馬でも障害競走が施行されていたが現在は行われておらず(但し、競馬法 競馬法施行令第17条の4により施行することはできる)、名古屋競馬場など一部の地方競馬場には障害コースの名残が見られる。したがって、アングロアラブ アラブの障害競走は日本に現存しない。