スポンサードリンク
建設をまるごと検索
建設を詳しく調べる
建設でお困りなら、ご確認してみてください。
お近くのバリアフリー(介護)リフォーム業者から
無料見積もりをお取り寄せして比較できます。
忙しいあなたにも手間なく、
ご自分の目線で、信頼の出来る工務店や
リフォーム業者をお選びいただき、
安心のリフォーム工事を行っていただければと思います。
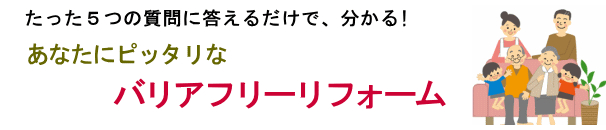
建設の関連情報
建設とは?
建設
建設(けんせつ、construction コンストラクション)は、建築(architecture)と土木(civil engineering)その他農分野の林業や造園の工事などや、海洋分野やプラント、「電設」という言葉(社団法人日本電設工業協会や住友電設株式会社などでいう電気設備の建設という意味での「電設」)や通信分野のインフラストラクチャーなどの基盤構築の分野の総称。ほか、言葉的には「建設的な意見」などのように積極、能動的なニュアンスが含まれながら使用される。
建築工事業と土木工事業の分野をあわせたものには、「土建」(どけん)という言葉がある。
建設と言う言葉自体は、明治時代に外来語を翻訳した時に中国由来の言葉から出来た和製熟語であるとされる。
明治に入り政府は太政官のもとに内務省 (日本) 内務省を設置し、土木寮を置く。土木寮は土木局に改称され 第二次大戦後、内務省土木局は後に置かれた都市計画局と合併し国土局と再改称されていた。その後内務省が解体されて独立した国土局が、「建設省」(現・国土交通省の前身の一つ)の看板をかけ、組の改名から建設会社、続いて建設業、建設業界の表現も生まれる。このときあたりから「建設」に土木と建築を併せ持つ概念が定着した。
建設機械
File:Hydraulic excavator.jpg thumb 250px 一般的な油圧ショベル(コマツ製)
建設機械(けんせつきかい、英語:construction equipment)は、土木・建築の作業(工事)に使われる機械の総称である。省略して建機(けんき)とも呼称される。人力で施工することが困難な作業を機械化したものがほとんどである。高度経済成長の時代に高層建築や道路整備などで建設機械が日本の社会資本整備に果たした成果は大きい。20世紀末から21世紀現在では、公共事業のコスト削減が叫ばれており建設機械にはさらなる作業の効率化などの役割が求められる。
国内での建設機械需要の50%強は、レンタル機の活用に移ってきている。建設業者の経営合理化に向け、機械経費削減のために、この流れはまだまだ加速している。
建設用機材
『建設機械』より : 建設機械(けんせつきかい)とは、土木・建築の作業(工事)に使われる機械の総称である。省略して建機(けんき)とも言う。人力で施工することが困難な作業を機械化したものがほとんどである。高度経済成長の時代に高層建築や道路整備などで建設機械が日本の社会資本整備に果たした成果は大きい。20世紀末から21世紀現在では、公共事業のコスト削減が叫ばれており建設機械にはさらなる作業の効率化などの役割が求められる。
国内での建設機械需要の50%強は、レンタル機の活用に移ってきており、建設業者の経営合理化に向け、機械経費削減のために、この流れはまだまだ加速している。
建設業
建設業(けんせつぎょう)とは、建設工事を請け負う営業のことをいい、日本においては、建設業法に規定する建設工事の種類にある工事の完成を請け負う営業をいう。
”建設業法は、以下で条数のみ記載する。”
特に注記がない場合、以降の記載はすべて日本の建設業についての記述である。
建設工事の請負を営業とするには、原則として請け負う業種ごとに許可を受けなければならない。
発注者から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工する者は、個人・法人の区別なく許可を受ける必要がある。下請負人からさらに請負をする孫請(まごうけ)と呼ぶ2次下請、更に2次下請から次の下請に発注する3次下請の曾孫請(ひまごうけ)以下の場合も同様である。従業員がおらず事業主ひとりだけで作業を行う建設業者もあり、この場合は一人親方(ひとりおやかた)と呼ばれることがある。後述の軽微な工事の範囲を超えれば事業主一人の場合でも建設業許可が必要である。
建設会社
『建設業』より : 建設業(けんせつぎょう)とは、建設工事を請け負う営業のことをいい、日本においては、建設業法に規定する建設工事の種類にある工事の完成を請け負う営業をいう。
特に注記がない場合、以降の記載はすべて日本の建設業についての記述である。
建設工事の請負を営業とするには、原則として許可を受けなければならない。
発注者から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工する者は、個人・法人の区別なく許可を受ける必要がある。下請負人からさらに請負をする孫請(まごうけ)と呼ぶ2次下請、更に2次下請から次の下請に発注する3次下請の曾孫請(ひまごうけ)以下の場合も同様である。従業員がおらず事業主ひとりだけで作業を行う建設業者もあり、この場合は一人親方(ひとりおやかた)と呼ばれることがある。後述の軽微な工事の範囲を超えれば事業主一人の場合でも建設業許可が必要である。
建設省
建設省(けんせつしょう)は、2001年(平成13年)1月5日まで存在した国土・都市計画、下水道整備、河川運河、水防砂防、道路、住居等に関する行政を取扱う中央省庁である。
建設省設置法(昭和23年7月8日、法律第113号)に基づき設置されていた。
1948年1月 - 建設院を設置した。
1949年 - 建設省と改称した。技官の影響が強く、技官出身者が事務次官に就任することもあった。
2001年1月6日 - 中央省庁再編の実施に伴い運輸省、国土庁、北海道開発庁と統合して、国土交通省を設置した。
内部部局
大臣官房
官庁営繕部
建設経済局
都市局
河川局
道路局
住宅局
施設機関
土木研究所
建設業経理事務士
建設業経理事務士(けんせつぎょうけいりじむし)は日本の建設業に関する民間資格で、財団法人建設業振興基金が主催している登録経理試験である。
建設業簿記の知識能力を級別に区分して試験を行っている。平成18年度より1級2級は建設業経理士検定試験が実施され合格者は1級(2級)建設業経理士となる。3級4級については従来通り建設業経理事務士検定試験が行われ合格者は3級(4級)建設業経理事務士となる。
試験開始時期:昭和56年度
検定試験と特別研修があり、特別研修の後で実施される試験に合格すれば、検定試験に合格したものと同じものとされる。平成20年度まで2級の特別研修が実施される予定であったが、法令の改正により平成18年度からは実施されなくなった。3級4級の特別研修は当面実施されると思われる。1級は検定試験で合格するしかない。検定試験は年1回、県庁所在地など主要都市にて3月第2日曜日に実施。平成18年の試験より4級の試験の実施場所が減り、主要な会場だけでしか受験できなくなった。
建設機械施工技士
建設機械施工技士(けんせつきかいせこうぎし)は、施工管理技士国家資格のうちの1つ。国土交通省管轄。
第一級と第二級に分かれ、第一級は各種建設機械を用いた施工における指導・監督的業務、第二級は第1種~第6種に別れそれぞれの機械を用いた施工において、運転・施工の業務に携わり、各機種の運転技術者、また一般建設業の現場の主任技術者として施工管理を行う。
国家試験は年1回実施される(実施は社団法人日本建設機械化協会)。
第1級 - トラクター系建設機械操作施工法、ショベル系建設機械操作施工法、モータ・グレーダ操作施工法、締固め建設機械操作施工法、舗装用建設機械操作施工法、基礎工事用建設機械操作施工法、建設機械組合せ施工法
建設学科
建設学科(けんせつがっか)は、大学の学科のひとつ。“学科”と名乗るのは短大以上である。建設(建築と土木)の設計・施工などの知識、技術修得を目指す教育、研究がおこなわれる。
設置している学校では、建築系と土木系の学科を統合して設置されている場合もあるが土木系の学科が名称変更した場合がほとんどである。「建設工学科」などとも呼ばれる。
建設という言葉を含む学科は以下のようになっている。土木系学科では建設の前に土木・建築・環境などをつける学科が多いことがわかる。また、神戸大学の建設学科は2007年に建築学科と市民工学科(Civil Engineeringを直訳したもの、土木科)に再分離した。
新潟大学
宇都宮大学
横浜国立大学
上記の大学では入学時、また年次途中で建築と土木に専攻を選択する。
建設コンサルタント
建設コンサルタント(けんせつコンサルタント)とは、土木技術を中心とした設計、計画業務を中心に官公庁並びに民間企業をクライアントとしてコンサルティングを行う業者をいう。事業所統計などではサービス業に分類される。受注先の割合は従前は官公庁(地方自治体含む)が大半を占めていたが、今後は公共事業の削減やPFI活用とも関連して民間関連業務にシフトしてゆくことが予想される。ODA関連による海外業務も多い。
関連団体として社団法人建設コンサルタンツ協会がある。
なお、広義の建設コンサルタントには、建築コンサルタント、マリンコンサルタント、環境コンサルタント、上下水道コンサルタント、廃棄物コンサルタント、地質コンサルタント、農業土木コンサルタントなどを含めることもある。
建設(けんせつ、construction コンストラクション)は、建築(architecture)と土木(civil engineering)その他農分野の林業や造園の工事などや、海洋分野やプラント、「電設」という言葉(社団法人日本電設工業協会や住友電設株式会社などでいう電気設備の建設という意味での「電設」)や通信分野のインフラストラクチャーなどの基盤構築の分野の総称。ほか、言葉的には「建設的な意見」などのように積極、能動的なニュアンスが含まれながら使用される。
建築工事業と土木工事業の分野をあわせたものには、「土建」(どけん)という言葉がある。
建設と言う言葉自体は、明治時代に外来語を翻訳した時に中国由来の言葉から出来た和製熟語であるとされる。
明治に入り政府は太政官のもとに内務省 (日本) 内務省を設置し、土木寮を置く。土木寮は土木局に改称され 第二次大戦後、内務省土木局は後に置かれた都市計画局と合併し国土局と再改称されていた。その後内務省が解体されて独立した国土局が、「建設省」(現・国土交通省の前身の一つ)の看板をかけ、組の改名から建設会社、続いて建設業、建設業界の表現も生まれる。このときあたりから「建設」に土木と建築を併せ持つ概念が定着した。
建設機械
File:Hydraulic excavator.jpg thumb 250px 一般的な油圧ショベル(コマツ製)
建設機械(けんせつきかい、英語:construction equipment)は、土木・建築の作業(工事)に使われる機械の総称である。省略して建機(けんき)とも呼称される。人力で施工することが困難な作業を機械化したものがほとんどである。高度経済成長の時代に高層建築や道路整備などで建設機械が日本の社会資本整備に果たした成果は大きい。20世紀末から21世紀現在では、公共事業のコスト削減が叫ばれており建設機械にはさらなる作業の効率化などの役割が求められる。
国内での建設機械需要の50%強は、レンタル機の活用に移ってきている。建設業者の経営合理化に向け、機械経費削減のために、この流れはまだまだ加速している。
建設用機材
『建設機械』より : 建設機械(けんせつきかい)とは、土木・建築の作業(工事)に使われる機械の総称である。省略して建機(けんき)とも言う。人力で施工することが困難な作業を機械化したものがほとんどである。高度経済成長の時代に高層建築や道路整備などで建設機械が日本の社会資本整備に果たした成果は大きい。20世紀末から21世紀現在では、公共事業のコスト削減が叫ばれており建設機械にはさらなる作業の効率化などの役割が求められる。
国内での建設機械需要の50%強は、レンタル機の活用に移ってきており、建設業者の経営合理化に向け、機械経費削減のために、この流れはまだまだ加速している。
建設業
建設業(けんせつぎょう)とは、建設工事を請け負う営業のことをいい、日本においては、建設業法に規定する建設工事の種類にある工事の完成を請け負う営業をいう。
”建設業法は、以下で条数のみ記載する。”
特に注記がない場合、以降の記載はすべて日本の建設業についての記述である。
建設工事の請負を営業とするには、原則として請け負う業種ごとに許可を受けなければならない。
発注者から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工する者は、個人・法人の区別なく許可を受ける必要がある。下請負人からさらに請負をする孫請(まごうけ)と呼ぶ2次下請、更に2次下請から次の下請に発注する3次下請の曾孫請(ひまごうけ)以下の場合も同様である。従業員がおらず事業主ひとりだけで作業を行う建設業者もあり、この場合は一人親方(ひとりおやかた)と呼ばれることがある。後述の軽微な工事の範囲を超えれば事業主一人の場合でも建設業許可が必要である。
建設会社
『建設業』より : 建設業(けんせつぎょう)とは、建設工事を請け負う営業のことをいい、日本においては、建設業法に規定する建設工事の種類にある工事の完成を請け負う営業をいう。
特に注記がない場合、以降の記載はすべて日本の建設業についての記述である。
建設工事の請負を営業とするには、原則として許可を受けなければならない。
発注者から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工する者は、個人・法人の区別なく許可を受ける必要がある。下請負人からさらに請負をする孫請(まごうけ)と呼ぶ2次下請、更に2次下請から次の下請に発注する3次下請の曾孫請(ひまごうけ)以下の場合も同様である。従業員がおらず事業主ひとりだけで作業を行う建設業者もあり、この場合は一人親方(ひとりおやかた)と呼ばれることがある。後述の軽微な工事の範囲を超えれば事業主一人の場合でも建設業許可が必要である。
建設省
建設省(けんせつしょう)は、2001年(平成13年)1月5日まで存在した国土・都市計画、下水道整備、河川運河、水防砂防、道路、住居等に関する行政を取扱う中央省庁である。
建設省設置法(昭和23年7月8日、法律第113号)に基づき設置されていた。
1948年1月 - 建設院を設置した。
1949年 - 建設省と改称した。技官の影響が強く、技官出身者が事務次官に就任することもあった。
2001年1月6日 - 中央省庁再編の実施に伴い運輸省、国土庁、北海道開発庁と統合して、国土交通省を設置した。
内部部局
大臣官房
官庁営繕部
建設経済局
都市局
河川局
道路局
住宅局
施設機関
土木研究所
建設業経理事務士
建設業経理事務士(けんせつぎょうけいりじむし)は日本の建設業に関する民間資格で、財団法人建設業振興基金が主催している登録経理試験である。
建設業簿記の知識能力を級別に区分して試験を行っている。平成18年度より1級2級は建設業経理士検定試験が実施され合格者は1級(2級)建設業経理士となる。3級4級については従来通り建設業経理事務士検定試験が行われ合格者は3級(4級)建設業経理事務士となる。
試験開始時期:昭和56年度
検定試験と特別研修があり、特別研修の後で実施される試験に合格すれば、検定試験に合格したものと同じものとされる。平成20年度まで2級の特別研修が実施される予定であったが、法令の改正により平成18年度からは実施されなくなった。3級4級の特別研修は当面実施されると思われる。1級は検定試験で合格するしかない。検定試験は年1回、県庁所在地など主要都市にて3月第2日曜日に実施。平成18年の試験より4級の試験の実施場所が減り、主要な会場だけでしか受験できなくなった。
建設機械施工技士
建設機械施工技士(けんせつきかいせこうぎし)は、施工管理技士国家資格のうちの1つ。国土交通省管轄。
第一級と第二級に分かれ、第一級は各種建設機械を用いた施工における指導・監督的業務、第二級は第1種~第6種に別れそれぞれの機械を用いた施工において、運転・施工の業務に携わり、各機種の運転技術者、また一般建設業の現場の主任技術者として施工管理を行う。
国家試験は年1回実施される(実施は社団法人日本建設機械化協会)。
第1級 - トラクター系建設機械操作施工法、ショベル系建設機械操作施工法、モータ・グレーダ操作施工法、締固め建設機械操作施工法、舗装用建設機械操作施工法、基礎工事用建設機械操作施工法、建設機械組合せ施工法
建設学科
建設学科(けんせつがっか)は、大学の学科のひとつ。“学科”と名乗るのは短大以上である。建設(建築と土木)の設計・施工などの知識、技術修得を目指す教育、研究がおこなわれる。
設置している学校では、建築系と土木系の学科を統合して設置されている場合もあるが土木系の学科が名称変更した場合がほとんどである。「建設工学科」などとも呼ばれる。
建設という言葉を含む学科は以下のようになっている。土木系学科では建設の前に土木・建築・環境などをつける学科が多いことがわかる。また、神戸大学の建設学科は2007年に建築学科と市民工学科(Civil Engineeringを直訳したもの、土木科)に再分離した。
新潟大学
宇都宮大学
横浜国立大学
上記の大学では入学時、また年次途中で建築と土木に専攻を選択する。
建設コンサルタント
建設コンサルタント(けんせつコンサルタント)とは、土木技術を中心とした設計、計画業務を中心に官公庁並びに民間企業をクライアントとしてコンサルティングを行う業者をいう。事業所統計などではサービス業に分類される。受注先の割合は従前は官公庁(地方自治体含む)が大半を占めていたが、今後は公共事業の削減やPFI活用とも関連して民間関連業務にシフトしてゆくことが予想される。ODA関連による海外業務も多い。
関連団体として社団法人建設コンサルタンツ協会がある。
なお、広義の建設コンサルタントには、建築コンサルタント、マリンコンサルタント、環境コンサルタント、上下水道コンサルタント、廃棄物コンサルタント、地質コンサルタント、農業土木コンサルタントなどを含めることもある。