スポンサードリンク
会社をまるごと検索
会社を詳しく調べる
会社でお困りなら、ご確認してみてください。
お近くのバリアフリー(介護)リフォーム業者から
無料見積もりをお取り寄せして比較できます。
忙しいあなたにも手間なく、
ご自分の目線で、信頼の出来る工務店や
リフォーム業者をお選びいただき、
安心のリフォーム工事を行っていただければと思います。
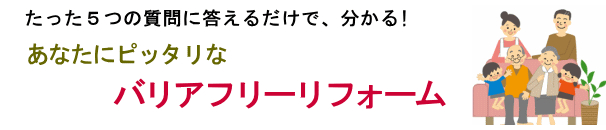
会社の関連情報
会社とは?
会社
会社(かいしゃ)は、日本法上、株式会社 (日本) 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。外国法における類似の概念(イギリスにおけるcompanyなど)の訳語としても用いられる。
本稿では、日本法上の会社に加え、それに相当する各国の企業形態についても記述する。
現行会社法上、会社の種類として株式会社 (日本) 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の四つが認められている(b:会社法第2条 会社法2条1号)。
従来は、商法第2編で定められていた株式会社、合名会社及び合資会社(さらに昔は株式合資会社も)に加え、昭和13年に制定された有限会社法で有限会社の設立が認められていたが、2005年(平成17年)制定の新会社法で有限会社は株式会社に統合された概要・第2の1(1)。有限会社法は会社法の施行(2006年5月1日)に伴って廃止され、従来の有限会社(旧有限会社)は、株式会社として存続することとされた(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2条1項)。この株式会社は、商号中に「有限会社」という文字を用いることとされ、特例有限会社と呼ばれる(同法3条)。また「株式会社」へと商号変更することにより通常の株式会社に移行することもできる(同法45条)。。それとともに、出資者の有限責任が確保され、会社の内部関係については組合的規律が適用される新たな会社類型として合同会社が創設された会社法575条以下、概要・第2の4(1)。。
会社法
会社法(かいしゃほう)とは、会社の設立・解散、組織、運営、資金調達(株式、社債等)、管理などについて規律する法 (法学) 法分野(実質的意味の会社法(英company law、米corporate law, corporation law))、あるいは、(当然ながら)そのような名称を有する法律(日本の会社法、英国のCompanies Actなど)をいう。
題名=会社法
番号=平成17年法律第86号
通称=なし
効力=現行法
種類=商事法
内容=会社の設立・組織・運営・管理等
関連=商法、民法、金融商品取引法、有限責任事業組合契約に関する法律
日本では、明治時代以来、会社法と題する法令は存在せず、商法第2編、有限会社法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法または監査特例法)など、会社に関係する法律を総称する名称として用いられていた。しかし、2005年の法改正によって、それらを統合・再編成する法律として会社法(平成17年法律第86号)と題する法律が制定された。2005年7月26日に公布、2006年5月1日に施行された(平成18年政令第77号)。
会社の役員
『役員 (会社)』より : 役員(やくいん)とは、会社の業務執行や監督を行う幹部職員のことをいう。いわゆる経営者。会社法における役員は、取締役、会計参与、監査役を指す(会社法329条参照)。しかし、一般的な意味では、それよりも広く役員 (会社)#執行役員 執行役員までを含む意味であることが多い。
役員は、会社の実質的所有者である社員(株主)とは必ずしも一致しない。特に株式が自由に譲渡できる公開会社である株式会社においては、取締役の資格を定款で株主に限定することができない(会社法331条2項)。これは、広く資本を集めるために、株主には経営能力を求めず、株主以外から経営能力のある人に経営を委任できるようにするためである。
会社役員
『役員 (会社)』より : 役員(やくいん)とは、会社の業務執行や監督を行う幹部職員のことをいう。いわゆる経営者。会社法における役員は、取締役、会計参与、監査役を指す(会社法329条参照)。しかし、一般的な意味では、それよりも広く役員 (会社)#執行役員 執行役員までを含む意味であることが多い。
役員は、会社の実質的所有者である社員(株主)とは必ずしも一致しない。特に株式が自由に譲渡できる公開会社である株式会社においては、取締役の資格を定款で株主に限定することができない(会社法331条2項)。これは、広く資本を集めるために、株主には経営能力を求めず、株主以外から経営能力のある人に経営を委任できるようにするためである。
会社別列車種別一覧
会社別列車種別一覧(かいしゃべつれっしゃしゅべついちらん)とは鉄道事業者別に、概ね停車駅の少ない順に示す。
一部の路線のみに走っている列車種別もある。
JRは普通列車のみ記載する。
この書体は乗車券の他に特別料金が必要。
函館本線:ホームライナー・快速「エアポート (列車) エアポート」・「ニセコライナー」>区間快速「いしかりライナー」>普通列車 普通
横浜線:快速列車 快速>各駅停車
宇都宮線(東北本線):ホームライナー>通勤快速・快速列車 快速「ラビット」・湘南新宿ライン直通快速列車 快速>普通列車 普通
京葉線:通勤快速>快速列車 快速(京葉快速)・武蔵野線直通快速(武蔵野快速)>各駅停車
会社合併
『企業合併』より : 企業合併(きぎょうがっぺい)とは、複数の企業が合併契約を締結し法定の手続を経た上で合体して一つの会社になること。
日本では、会社法や(旧)有限会社法に規定されている。企業組織再編の手法の一つで、法人と法人とが結合する手法として、比較的古くから用いられてきた。
従来は、企業の再編や統合に企業合併が多く行われていたが、1998年の商法改正で、純粋持株会社の設立が可能になったため、株式移転などにより持株会社を設立し、持株会社の下に各企業を統合する手法も行われるようになっている。
企業合併を行う場合の方式の法的分類としては、吸収合併と新設合併の区別がある。
会社員
『サラリーマン』より : サラリーマンとは、給料で生計を立てている人である。和製英語であるが、日本人が海外において自らの職業をさす英単語として使い続けたことや、漫画やアニメなどによる日本文化の普及により、欧米でも「日本の(ホワイトカラー)ビジネスマン」を指す普通名詞(Salaryman)として浸透しつつある。日本文化を扱った新聞記事や書籍などで度々使用されている。
サラリーマンは、広義には公務員や団体職員、ブルーカラーなどを含む言葉であるが、現在では主に会社に雇用されているホワイトカラー労働者を指して用いられる場合が多い。
多くの場合、安定的に給料を得ている人に対して使用される言葉であるため、給与所得者であっても、俳優や歌手などの芸能関係者や、ホステスやホストなどのいわゆる水商売関係の職業、日雇い労働者は含めないことが多い。医師や弁護士などの専門職も同様である。自営業(画家や音楽家などの芸術家を含む)や会社役員、議員などは給与所得者ではないのでサラリーマンではない。
会社更生法
題名 会社更生法
通称 なし
番号 平成14年12月13日法律第154号
効力 現行法
種類 倒産法
内容 株式会社の更生手続
関連 民事再生法破産法
会社更生法(かいしゃこうせいほう)は、経営困難ではあるが再建の見込みのある株式会社について、事業の維持・更生を目的としてなされる更生手続を定めるために制定された日本の法律である。日本における倒産法の一つ。最終改正は2006年(平成18年)3月31日法律第10号。なお、会社更生法に基づく更生手続のことを、「会社更生手続」と呼ぶことが多い。
第二次世界大戦後、米国で実績を挙げつつあった当時の連邦倒産法第10章Corporate Reorganization(会社更生)の制度を日本に移植するべく、昭和27年に制定された(昭和27年法律第172号)。その後、昭和42年に会社更生手続の濫用防止、債権者である取引先中小企業の保護の観点から実質改正がされ、さらに、2002年(平成14年)に会社更生法の全部改正をする新しい会社更生法(平成14年法律第154号)が制定され、その施行(平成15年4月1日)に伴い以前の会社更生法は廃止された。
会社更正法
『会社更生法』より : 題名=会社更生法
通称=なし
番号=平成14年12月13日法律第154号
効力=現行法
種類=倒産法
内容=会社更生手続
関連=民事再生法
破産法
会社更生法(かいしゃこうせいほう)とは、経営困難ではあるが再建の見込みのある株式会社について、事業の維持・更生を目的としてなされる会社更生手続を定めるために制定された日本の法律である。最終改正は2006年(平成18年)3月31日法律第10号。
第二次世界大戦後、米国で実績を挙げつつあった当時の連邦破産法第10章のコーポレイト・リオーガニゼイション(Corporate Reorganization,会社更生)の制度を日本に移植するべく、昭和27年に制定された(昭和27年法律第172号)。その後、昭和42年に会社更生手続の濫用防止、債権者である取引先中小企業の保護の観点から実質改正がされ、さらに、2002年(平成14年)に会社更生法の全部改正をする新しい会社更生法(平成14年法律第154号)が制定され、その施行(平成15年4月1日)に伴い以前の会社更生法は実質的に廃止された。
会社更生
『会社更生法』より : 題名=会社更生法
通称=なし
番号=平成14年12月13日法律第154号
効力=現行法
種類=倒産法
内容=会社更生手続
関連=民事再生法
破産法
会社更生法(かいしゃこうせいほう)とは、経営困難ではあるが再建の見込みのある株式会社について、事業の維持・更生を目的としてなされる会社更生手続を定めるために制定された日本の法律である。最終改正は2006年(平成18年)3月31日法律第10号。
第二次世界大戦後、米国で実績を挙げつつあった当時の連邦破産法第10章のコーポレイト・リオーガニゼイション(Corporate Reorganization,会社更生)の制度を日本に移植するべく、昭和27年に制定された(昭和27年法律第172号)。その後、昭和42年に会社更生手続の濫用防止、債権者である取引先中小企業の保護の観点から実質改正がされ、さらに、2002年(平成14年)に会社更生法の全部改正をする新しい会社更生法(平成14年法律第154号)が制定され、その施行(平成15年4月1日)に伴い以前の会社更生法は実質的に廃止された。
会社(かいしゃ)は、日本法上、株式会社 (日本) 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。外国法における類似の概念(イギリスにおけるcompanyなど)の訳語としても用いられる。
本稿では、日本法上の会社に加え、それに相当する各国の企業形態についても記述する。
現行会社法上、会社の種類として株式会社 (日本) 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の四つが認められている(b:会社法第2条 会社法2条1号)。
従来は、商法第2編で定められていた株式会社、合名会社及び合資会社(さらに昔は株式合資会社も)に加え、昭和13年に制定された有限会社法で有限会社の設立が認められていたが、2005年(平成17年)制定の新会社法で有限会社は株式会社に統合された概要・第2の1(1)。有限会社法は会社法の施行(2006年5月1日)に伴って廃止され、従来の有限会社(旧有限会社)は、株式会社として存続することとされた(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2条1項)。この株式会社は、商号中に「有限会社」という文字を用いることとされ、特例有限会社と呼ばれる(同法3条)。また「株式会社」へと商号変更することにより通常の株式会社に移行することもできる(同法45条)。。それとともに、出資者の有限責任が確保され、会社の内部関係については組合的規律が適用される新たな会社類型として合同会社が創設された会社法575条以下、概要・第2の4(1)。。
会社法
会社法(かいしゃほう)とは、会社の設立・解散、組織、運営、資金調達(株式、社債等)、管理などについて規律する法 (法学) 法分野(実質的意味の会社法(英company law、米corporate law, corporation law))、あるいは、(当然ながら)そのような名称を有する法律(日本の会社法、英国のCompanies Actなど)をいう。
題名=会社法
番号=平成17年法律第86号
通称=なし
効力=現行法
種類=商事法
内容=会社の設立・組織・運営・管理等
関連=商法、民法、金融商品取引法、有限責任事業組合契約に関する法律
日本では、明治時代以来、会社法と題する法令は存在せず、商法第2編、有限会社法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法または監査特例法)など、会社に関係する法律を総称する名称として用いられていた。しかし、2005年の法改正によって、それらを統合・再編成する法律として会社法(平成17年法律第86号)と題する法律が制定された。2005年7月26日に公布、2006年5月1日に施行された(平成18年政令第77号)。
会社の役員
『役員 (会社)』より : 役員(やくいん)とは、会社の業務執行や監督を行う幹部職員のことをいう。いわゆる経営者。会社法における役員は、取締役、会計参与、監査役を指す(会社法329条参照)。しかし、一般的な意味では、それよりも広く役員 (会社)#執行役員 執行役員までを含む意味であることが多い。
役員は、会社の実質的所有者である社員(株主)とは必ずしも一致しない。特に株式が自由に譲渡できる公開会社である株式会社においては、取締役の資格を定款で株主に限定することができない(会社法331条2項)。これは、広く資本を集めるために、株主には経営能力を求めず、株主以外から経営能力のある人に経営を委任できるようにするためである。
会社役員
『役員 (会社)』より : 役員(やくいん)とは、会社の業務執行や監督を行う幹部職員のことをいう。いわゆる経営者。会社法における役員は、取締役、会計参与、監査役を指す(会社法329条参照)。しかし、一般的な意味では、それよりも広く役員 (会社)#執行役員 執行役員までを含む意味であることが多い。
役員は、会社の実質的所有者である社員(株主)とは必ずしも一致しない。特に株式が自由に譲渡できる公開会社である株式会社においては、取締役の資格を定款で株主に限定することができない(会社法331条2項)。これは、広く資本を集めるために、株主には経営能力を求めず、株主以外から経営能力のある人に経営を委任できるようにするためである。
会社別列車種別一覧
会社別列車種別一覧(かいしゃべつれっしゃしゅべついちらん)とは鉄道事業者別に、概ね停車駅の少ない順に示す。
一部の路線のみに走っている列車種別もある。
JRは普通列車のみ記載する。
この書体は乗車券の他に特別料金が必要。
函館本線:ホームライナー・快速「エアポート (列車) エアポート」・「ニセコライナー」>区間快速「いしかりライナー」>普通列車 普通
横浜線:快速列車 快速>各駅停車
宇都宮線(東北本線):ホームライナー>通勤快速・快速列車 快速「ラビット」・湘南新宿ライン直通快速列車 快速>普通列車 普通
京葉線:通勤快速>快速列車 快速(京葉快速)・武蔵野線直通快速(武蔵野快速)>各駅停車
会社合併
『企業合併』より : 企業合併(きぎょうがっぺい)とは、複数の企業が合併契約を締結し法定の手続を経た上で合体して一つの会社になること。
日本では、会社法や(旧)有限会社法に規定されている。企業組織再編の手法の一つで、法人と法人とが結合する手法として、比較的古くから用いられてきた。
従来は、企業の再編や統合に企業合併が多く行われていたが、1998年の商法改正で、純粋持株会社の設立が可能になったため、株式移転などにより持株会社を設立し、持株会社の下に各企業を統合する手法も行われるようになっている。
企業合併を行う場合の方式の法的分類としては、吸収合併と新設合併の区別がある。
会社員
『サラリーマン』より : サラリーマンとは、給料で生計を立てている人である。和製英語であるが、日本人が海外において自らの職業をさす英単語として使い続けたことや、漫画やアニメなどによる日本文化の普及により、欧米でも「日本の(ホワイトカラー)ビジネスマン」を指す普通名詞(Salaryman)として浸透しつつある。日本文化を扱った新聞記事や書籍などで度々使用されている。
サラリーマンは、広義には公務員や団体職員、ブルーカラーなどを含む言葉であるが、現在では主に会社に雇用されているホワイトカラー労働者を指して用いられる場合が多い。
多くの場合、安定的に給料を得ている人に対して使用される言葉であるため、給与所得者であっても、俳優や歌手などの芸能関係者や、ホステスやホストなどのいわゆる水商売関係の職業、日雇い労働者は含めないことが多い。医師や弁護士などの専門職も同様である。自営業(画家や音楽家などの芸術家を含む)や会社役員、議員などは給与所得者ではないのでサラリーマンではない。
会社更生法
題名 会社更生法
通称 なし
番号 平成14年12月13日法律第154号
効力 現行法
種類 倒産法
内容 株式会社の更生手続
関連 民事再生法破産法
会社更生法(かいしゃこうせいほう)は、経営困難ではあるが再建の見込みのある株式会社について、事業の維持・更生を目的としてなされる更生手続を定めるために制定された日本の法律である。日本における倒産法の一つ。最終改正は2006年(平成18年)3月31日法律第10号。なお、会社更生法に基づく更生手続のことを、「会社更生手続」と呼ぶことが多い。
第二次世界大戦後、米国で実績を挙げつつあった当時の連邦倒産法第10章Corporate Reorganization(会社更生)の制度を日本に移植するべく、昭和27年に制定された(昭和27年法律第172号)。その後、昭和42年に会社更生手続の濫用防止、債権者である取引先中小企業の保護の観点から実質改正がされ、さらに、2002年(平成14年)に会社更生法の全部改正をする新しい会社更生法(平成14年法律第154号)が制定され、その施行(平成15年4月1日)に伴い以前の会社更生法は廃止された。
会社更正法
『会社更生法』より : 題名=会社更生法
通称=なし
番号=平成14年12月13日法律第154号
効力=現行法
種類=倒産法
内容=会社更生手続
関連=民事再生法
破産法
会社更生法(かいしゃこうせいほう)とは、経営困難ではあるが再建の見込みのある株式会社について、事業の維持・更生を目的としてなされる会社更生手続を定めるために制定された日本の法律である。最終改正は2006年(平成18年)3月31日法律第10号。
第二次世界大戦後、米国で実績を挙げつつあった当時の連邦破産法第10章のコーポレイト・リオーガニゼイション(Corporate Reorganization,会社更生)の制度を日本に移植するべく、昭和27年に制定された(昭和27年法律第172号)。その後、昭和42年に会社更生手続の濫用防止、債権者である取引先中小企業の保護の観点から実質改正がされ、さらに、2002年(平成14年)に会社更生法の全部改正をする新しい会社更生法(平成14年法律第154号)が制定され、その施行(平成15年4月1日)に伴い以前の会社更生法は実質的に廃止された。
会社更生
『会社更生法』より : 題名=会社更生法
通称=なし
番号=平成14年12月13日法律第154号
効力=現行法
種類=倒産法
内容=会社更生手続
関連=民事再生法
破産法
会社更生法(かいしゃこうせいほう)とは、経営困難ではあるが再建の見込みのある株式会社について、事業の維持・更生を目的としてなされる会社更生手続を定めるために制定された日本の法律である。最終改正は2006年(平成18年)3月31日法律第10号。
第二次世界大戦後、米国で実績を挙げつつあった当時の連邦破産法第10章のコーポレイト・リオーガニゼイション(Corporate Reorganization,会社更生)の制度を日本に移植するべく、昭和27年に制定された(昭和27年法律第172号)。その後、昭和42年に会社更生手続の濫用防止、債権者である取引先中小企業の保護の観点から実質改正がされ、さらに、2002年(平成14年)に会社更生法の全部改正をする新しい会社更生法(平成14年法律第154号)が制定され、その施行(平成15年4月1日)に伴い以前の会社更生法は実質的に廃止された。