スポンサードリンク
介護をまるごと検索
介護を詳しく調べる
介護でお困りなら、ご確認してみてください。
お近くのバリアフリー(介護)リフォーム業者から
無料見積もりをお取り寄せして比較できます。
忙しいあなたにも手間なく、
ご自分の目線で、信頼の出来る工務店や
リフォーム業者をお選びいただき、
安心のリフォーム工事を行っていただければと思います。
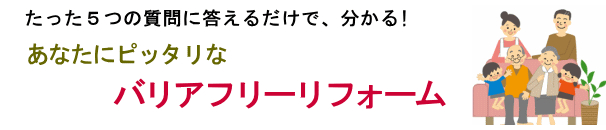
介護の関連情報
介護とは?
介護
介護(かいご)とは、障害者の生活支援をすること。あるいは高齢者・病人などを介抱し世話をすること。
日本で「介護」という言葉が法令上で確認されるのは、1892年の陸軍軍人傷痍軍人 傷痍疾病恩給等差例からであり、介護は施策としてではなく、恩給の給付基準としての概念であった。「介護」という言葉が主体的に使われるようになったのは、1970年代後半からの障害者による公的介護保障の要求運動からである。それ以前の「『障害者の面倒を見るのは親がやって当り前』という社会の考え方からでは障害者は施設に追いやられる」という危機感からそのような運動が発生した。
公的介護保障の要求を受けて、介護人派遣事業が制度化され始めたのは1980年代半ばからであるが、障害者にとって保障と呼ぶにはほど遠いものであった。地方自治体による高齢者の訪問介護・看護事業は1960年代より始まったが、理念的には家族介護への支えであって、その考え方は現在でも受け継がれている。医療にクオリティ・オブ・ライフ QOLの考えが普及すると、介護にも導入され、介護によって病人、高齢者の生活の質(QOL)を高め、QOLのさらなる向上に貢献することもまた介護の目的とされている。
介護福祉士国家試験
介護福祉士国家試験(かいごふくししこっかしけん)とは、厚生労働省の外郭団体、財団法人社会福祉振興・試験センターが実施する、第一次試験と第二次試験からなる国家試験をいう。2007年1月に19回目が実施された。受験者数は毎年増加の一途をたどり、第19回試験ではおよそ14万6千人が受験した。
介護福祉士国家試験を受験するには下記の要件を満たす必要がある。
3年以上介護等の業務に従事した者
福祉系高等学校を卒業した者
介護福祉士国家試験は、第一次試験(筆記試験)、第二次試験(実技試験)からなる。
第一次試験は1月下旬、第二次試験は3月上旬にそれぞれ北海道、青森県、宮城県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、鹿児島県、沖縄県で行われる。ただし、介護技術講習会を受講し修了した場合には、実技試験は3回まで免除され、第一次試験のみで合否が決定される。
介護保険制度
狭義には、社会の高齢化に対応し、2000年(平成12年)4月1日から施行された日本の社会保険制度。要介護状態又は要支援状態にある人が介護サービスを利用する際、その費用(給付費)を被保険者から徴収する保険料だけでなく、国・都道府県・市町村が負担する特徴を持つ。
以下では、日本の公的介護保険制度について記述する。
高齢化や核家族化の進展等により、要介護者を社会全体で支える新たな仕組みとして2000年4月より介護保険制度が導入された。日本の制度は、おおむねドイツの介護保険制度をモデルに導入されたと言われている。介護保険料については、新たな負担に対する世論の反発を避けるため、導入当初は半年間徴収が凍結され、2000年10月から半額徴収、2001年10月から全額徴収という経緯をたどっている。
介護保険
『介護保険制度』より : 介護保険制度(かいごほけんせいど)は社会の高齢化に対応し、日本で2000年(平成12年)度から介護保険法により設けられた社会保険制度。
法附則の規定に基づく制度全般の見直し時期を迎え、2006年4月から新たなシステムなどがスタートした。改革の目玉の1つは介護予防を重視したシステムへの転換にある。
予防プランやリハビリによる、要介護状態の軽減、悪化防止を目的とした『新予防給付』と、市町村が予防メニューを実施する『地域支援事業』の2本立て構成になっている。
要介護状態にある人が介護サービスを利用する際、その費用を被保険者から徴収する保険料だけでなく、国・都道府県・市町村が負担する特徴を持つ。現行の制度では、サービス利用者の利用料負担は1割。介護保険サービスの財源は、65歳以上の第1号被保険者と40〜64歳の第2号被保険者が50%、残りの50%を国(25%)と都道府県(12.5%)、市区町村(12.5%)で負担している。
介護認定
『介護保険制度』より : 介護保険制度(かいごほけんせいど)は社会の高齢化に対応し、日本で2000年(平成12年)度から介護保険法により設けられた社会保険制度。
法附則の規定に基づく制度全般の見直し時期を迎え、2006年4月から新たなシステムなどがスタートした。改革の目玉の1つは介護予防を重視したシステムへの転換にある。
予防プランやリハビリによる、要介護状態の軽減、悪化防止を目的とした『新予防給付』と、市町村が予防メニューを実施する『地域支援事業』の2本立て構成になっている。
要介護状態にある人が介護サービスを利用する際、その費用を被保険者から徴収する保険料だけでなく、国・都道府県・市町村が負担する特徴を持つ。現行の制度では、サービス利用者の利用料負担は1割。介護保険サービスの財源は、65歳以上の第1号被保険者と40〜64歳の第2号被保険者が50%、残りの50%を国(25%)と都道府県(12.5%)、市区町村(12.5%)で負担している。
介護サービス事業者の種類
介護サービス事業所は、介護保険制度において、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となったもの(要介護者等)に対し、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービス(総称して介護サービスという)を提供する事業所。
一般には、一定の要件を満たして都道府県の事業所指定を受けた指定介護サービス事業所を指すが、広義には、保険者(市町村)がそのサービスについて一定水準を満たすと認め、在宅給付を行う基準該当介護サービス事業所も含まれる。
介護保険法では、在宅の要介護者等に対し介護サービスを提供する#居宅サービス事業者と、要介護者を入所させて介護サービスを提供する#介護保険施設が定義されているが、これらを包括した概念である介護サービス事業者は定義されていない。
介護福祉士
介護福祉士の活動場所としては、特別養護老人ホーム、デイケアセンターや障害福祉サービス事業所、その他の社会福祉施設があげられる。また、在宅で生活している要介護者の自宅に通って援助する訪問介護員(ホームヘルパー)にも介護福祉士資格は有用である。社会福祉士がソーシャルワーカーという英語名でも呼ばれるように、介護福祉士についてもケアワーカーという呼び方をすることもある。
今後は、この職種の専門性を深めていくこと、他の医療、看護、リハビリテーションなどの職種との連携、相互理解などその職域の発展のためなされなければならないことが多い。介護福祉学会も誕生し、介護福祉学といった専門分野もその産声を上げた。しかし、介護福祉士の資格を取得してもその社会的地位は看護師と同等とは言い難く(例えば厚生労働省が定めたグループホームの人員配置には看護師はあるが介護福祉士の規定はない等)、その業務内容が苛酷であることから離職率が非常に高い。その背景として、過酷な労働に対して給与が安いという問題がある。また苛酷かつ、給与が低いことからさらに敬遠され人材が不足しているため、勤務がより苛酷になるという悪循環が生じている。
介護老人福祉施設
介護老人福祉施設(かいごろうじんふくししせつ)とは、介護サービス事業者の種類 介護老人保健施設および介護サービス事業者の種類 指定介護療養型医療施設とともに、介護サービス事業者の種類 介護保険施設の一つである。
特別養護老人ホームであって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行なうことを目的とする施設をいう。
老人福祉法に基づく施設である特別養護老人ホームと、ほぼ同じものである。
介護保険法に基づき、都道府県知事から指定を受けることによって『指定介護老人福祉施設』となり、介護保険による施設サービスの対象になる。
介護保険法
題名=介護保険法
番号=平成9年法律第123号
通称=なし
効力=現行法
種類=社会保障法
内容=介護保険について
関連=介護従事者等の人材確保のための介護従事者等の処遇改善に関する法律、老人福祉法、老人保健法、医療法、国民健康保険制度 国民健康保険法、国民年金法
介護保険法(かいごほけんほう;(平成9年12月17日法律第123号)は、要介護者(同法7条3項)等について、介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定めることを目的とする法律である(同法1条)。
第1章 - 総則(第1条~第8条)
第2章 - 被保険者(第9条~第13条)
第3章 - 介護認定審査会(第14条~第17条)
第4章 - 保険給付
第1節 - 通則(第18条~第26条)
第2節 - 認定(第27条~第39条)
*第27条(要介護認定)
介護等の体験
介護等の体験(かいごとうのたいけん)とは、義務教育諸学校の教員の免許状(教員免許状)の授与を受ける際に必要とされる介護などを基調とする体験活動のことである。
小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律
教育職員免許法(上記法律により規定が読み替えられる)
法律施行により、義務教育諸学校の教員免許状の授与を受けるにあたって社会福祉施設や特殊教育諸学校などにおいて、文部科学大臣が定める期間(7日間)、介護等の体験を行い、施設や学校が発行する体験に関する証明書を免許状授与申請の際提出することが必要となった。
介護(かいご)とは、障害者の生活支援をすること。あるいは高齢者・病人などを介抱し世話をすること。
日本で「介護」という言葉が法令上で確認されるのは、1892年の陸軍軍人傷痍軍人 傷痍疾病恩給等差例からであり、介護は施策としてではなく、恩給の給付基準としての概念であった。「介護」という言葉が主体的に使われるようになったのは、1970年代後半からの障害者による公的介護保障の要求運動からである。それ以前の「『障害者の面倒を見るのは親がやって当り前』という社会の考え方からでは障害者は施設に追いやられる」という危機感からそのような運動が発生した。
公的介護保障の要求を受けて、介護人派遣事業が制度化され始めたのは1980年代半ばからであるが、障害者にとって保障と呼ぶにはほど遠いものであった。地方自治体による高齢者の訪問介護・看護事業は1960年代より始まったが、理念的には家族介護への支えであって、その考え方は現在でも受け継がれている。医療にクオリティ・オブ・ライフ QOLの考えが普及すると、介護にも導入され、介護によって病人、高齢者の生活の質(QOL)を高め、QOLのさらなる向上に貢献することもまた介護の目的とされている。
介護福祉士国家試験
介護福祉士国家試験(かいごふくししこっかしけん)とは、厚生労働省の外郭団体、財団法人社会福祉振興・試験センターが実施する、第一次試験と第二次試験からなる国家試験をいう。2007年1月に19回目が実施された。受験者数は毎年増加の一途をたどり、第19回試験ではおよそ14万6千人が受験した。
介護福祉士国家試験を受験するには下記の要件を満たす必要がある。
3年以上介護等の業務に従事した者
福祉系高等学校を卒業した者
介護福祉士国家試験は、第一次試験(筆記試験)、第二次試験(実技試験)からなる。
第一次試験は1月下旬、第二次試験は3月上旬にそれぞれ北海道、青森県、宮城県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、鹿児島県、沖縄県で行われる。ただし、介護技術講習会を受講し修了した場合には、実技試験は3回まで免除され、第一次試験のみで合否が決定される。
介護保険制度
狭義には、社会の高齢化に対応し、2000年(平成12年)4月1日から施行された日本の社会保険制度。要介護状態又は要支援状態にある人が介護サービスを利用する際、その費用(給付費)を被保険者から徴収する保険料だけでなく、国・都道府県・市町村が負担する特徴を持つ。
以下では、日本の公的介護保険制度について記述する。
高齢化や核家族化の進展等により、要介護者を社会全体で支える新たな仕組みとして2000年4月より介護保険制度が導入された。日本の制度は、おおむねドイツの介護保険制度をモデルに導入されたと言われている。介護保険料については、新たな負担に対する世論の反発を避けるため、導入当初は半年間徴収が凍結され、2000年10月から半額徴収、2001年10月から全額徴収という経緯をたどっている。
介護保険
『介護保険制度』より : 介護保険制度(かいごほけんせいど)は社会の高齢化に対応し、日本で2000年(平成12年)度から介護保険法により設けられた社会保険制度。
法附則の規定に基づく制度全般の見直し時期を迎え、2006年4月から新たなシステムなどがスタートした。改革の目玉の1つは介護予防を重視したシステムへの転換にある。
予防プランやリハビリによる、要介護状態の軽減、悪化防止を目的とした『新予防給付』と、市町村が予防メニューを実施する『地域支援事業』の2本立て構成になっている。
要介護状態にある人が介護サービスを利用する際、その費用を被保険者から徴収する保険料だけでなく、国・都道府県・市町村が負担する特徴を持つ。現行の制度では、サービス利用者の利用料負担は1割。介護保険サービスの財源は、65歳以上の第1号被保険者と40〜64歳の第2号被保険者が50%、残りの50%を国(25%)と都道府県(12.5%)、市区町村(12.5%)で負担している。
介護認定
『介護保険制度』より : 介護保険制度(かいごほけんせいど)は社会の高齢化に対応し、日本で2000年(平成12年)度から介護保険法により設けられた社会保険制度。
法附則の規定に基づく制度全般の見直し時期を迎え、2006年4月から新たなシステムなどがスタートした。改革の目玉の1つは介護予防を重視したシステムへの転換にある。
予防プランやリハビリによる、要介護状態の軽減、悪化防止を目的とした『新予防給付』と、市町村が予防メニューを実施する『地域支援事業』の2本立て構成になっている。
要介護状態にある人が介護サービスを利用する際、その費用を被保険者から徴収する保険料だけでなく、国・都道府県・市町村が負担する特徴を持つ。現行の制度では、サービス利用者の利用料負担は1割。介護保険サービスの財源は、65歳以上の第1号被保険者と40〜64歳の第2号被保険者が50%、残りの50%を国(25%)と都道府県(12.5%)、市区町村(12.5%)で負担している。
介護サービス事業者の種類
介護サービス事業所は、介護保険制度において、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となったもの(要介護者等)に対し、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービス(総称して介護サービスという)を提供する事業所。
一般には、一定の要件を満たして都道府県の事業所指定を受けた指定介護サービス事業所を指すが、広義には、保険者(市町村)がそのサービスについて一定水準を満たすと認め、在宅給付を行う基準該当介護サービス事業所も含まれる。
介護保険法では、在宅の要介護者等に対し介護サービスを提供する#居宅サービス事業者と、要介護者を入所させて介護サービスを提供する#介護保険施設が定義されているが、これらを包括した概念である介護サービス事業者は定義されていない。
介護福祉士
介護福祉士の活動場所としては、特別養護老人ホーム、デイケアセンターや障害福祉サービス事業所、その他の社会福祉施設があげられる。また、在宅で生活している要介護者の自宅に通って援助する訪問介護員(ホームヘルパー)にも介護福祉士資格は有用である。社会福祉士がソーシャルワーカーという英語名でも呼ばれるように、介護福祉士についてもケアワーカーという呼び方をすることもある。
今後は、この職種の専門性を深めていくこと、他の医療、看護、リハビリテーションなどの職種との連携、相互理解などその職域の発展のためなされなければならないことが多い。介護福祉学会も誕生し、介護福祉学といった専門分野もその産声を上げた。しかし、介護福祉士の資格を取得してもその社会的地位は看護師と同等とは言い難く(例えば厚生労働省が定めたグループホームの人員配置には看護師はあるが介護福祉士の規定はない等)、その業務内容が苛酷であることから離職率が非常に高い。その背景として、過酷な労働に対して給与が安いという問題がある。また苛酷かつ、給与が低いことからさらに敬遠され人材が不足しているため、勤務がより苛酷になるという悪循環が生じている。
介護老人福祉施設
介護老人福祉施設(かいごろうじんふくししせつ)とは、介護サービス事業者の種類 介護老人保健施設および介護サービス事業者の種類 指定介護療養型医療施設とともに、介護サービス事業者の種類 介護保険施設の一つである。
特別養護老人ホームであって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行なうことを目的とする施設をいう。
老人福祉法に基づく施設である特別養護老人ホームと、ほぼ同じものである。
介護保険法に基づき、都道府県知事から指定を受けることによって『指定介護老人福祉施設』となり、介護保険による施設サービスの対象になる。
介護保険法
題名=介護保険法
番号=平成9年法律第123号
通称=なし
効力=現行法
種類=社会保障法
内容=介護保険について
関連=介護従事者等の人材確保のための介護従事者等の処遇改善に関する法律、老人福祉法、老人保健法、医療法、国民健康保険制度 国民健康保険法、国民年金法
介護保険法(かいごほけんほう;(平成9年12月17日法律第123号)は、要介護者(同法7条3項)等について、介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定めることを目的とする法律である(同法1条)。
第1章 - 総則(第1条~第8条)
第2章 - 被保険者(第9条~第13条)
第3章 - 介護認定審査会(第14条~第17条)
第4章 - 保険給付
第1節 - 通則(第18条~第26条)
第2節 - 認定(第27条~第39条)
*第27条(要介護認定)
介護等の体験
介護等の体験(かいごとうのたいけん)とは、義務教育諸学校の教員の免許状(教員免許状)の授与を受ける際に必要とされる介護などを基調とする体験活動のことである。
小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律
教育職員免許法(上記法律により規定が読み替えられる)
法律施行により、義務教育諸学校の教員免許状の授与を受けるにあたって社会福祉施設や特殊教育諸学校などにおいて、文部科学大臣が定める期間(7日間)、介護等の体験を行い、施設や学校が発行する体験に関する証明書を免許状授与申請の際提出することが必要となった。