スポンサードリンク
トイレをまるごと検索
トイレを詳しく調べる
トイレでお困りなら、ご確認してみてください。
お近くのバリアフリー(介護)リフォーム業者から
無料見積もりをお取り寄せして比較できます。
忙しいあなたにも手間なく、
ご自分の目線で、信頼の出来る工務店や
リフォーム業者をお選びいただき、
安心のリフォーム工事を行っていただければと思います。
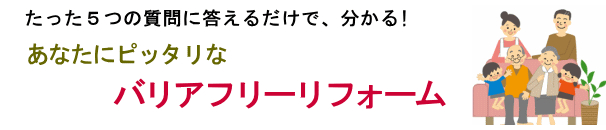
トイレの関連情報
トイレとは?
トイレ
『便所』より : 便所(べんじょ、英”Toilet”)とは、大小便など排泄の用を足すするための設備を備えている場所。様々な呼称がある。呼称に関しては後述の便所#呼称について 呼称についてを参照されたし。
この施設は、悪臭を放ち周辺の環境を汚損するおそれのある汚物(主に糞・尿・嘔吐 吐瀉物)を衛生的に処分するための機能を持っている。近年の文明社会の多くでは、これら施設の多くは水洗(水の流れる力を用いて、強制的に汚物を流し去る)の物が見られるが、宇宙船の中では乾燥させたりするものもあり、1970年の日本万国博覧会 大阪万博では都市ガス ガスによる燃焼方式も見られるなど、衛生的に処理できれば、特にその方法は問わない。乾燥地帯では砂を掛けて糞便を乾燥させて処分する様式も見られる。(水洗便器の詳細は便器が詳しい)
トイレット
『便所』より : 便所(べんじょ、英”Toilet”)とは、大小便など排泄の用を足すするための設備を備えている場所。様々な呼称がある。呼称に関しては後述の便所#呼称について 呼称についてを参照されたし。
この施設は、悪臭を放ち周辺の環境を汚損するおそれのある汚物(主に糞・尿・嘔吐 吐瀉物)を衛生的に処分するための機能を持っている。近年の文明社会の多くでは、これら施設の多くは水洗(水の流れる力を用いて、強制的に汚物を流し去る)の物が見られるが、宇宙船の中では乾燥させたりするものもあり、1970年の日本万国博覧会 大阪万博では都市ガス ガスによる燃焼方式も見られるなど、衛生的に処理できれば、特にその方法は問わない。乾燥地帯では砂を掛けて糞便を乾燥させて処分する様式も見られる。(水洗便器の詳細は便器が詳しい)
トイレットトレーニング
トイレットトレーニングとは、排泄に絡む便所の使用に関する訓練を言う行為。主に家庭内で最も基本的な躾として行われる。
人間の幼児の場合には、おむつの取れた後、一般の便所 トイレで用が足せるようにすることがトイレットトレーニングである。お尻のしつけとも言う。
排泄の間隔が2〜3時間おきになって、一人歩きができる様になっていく年齢から開始される物である。
お座りができるようになれば、おまるに座らせて排泄させることも不可能ではないが、早くからトイレでできるできないは赤ん坊によって能力、個人差が大きく、一旦トレーニングに成功したとしても逆戻りすることが少なくない(オムツの節約にはなるが)。
トイレトレーニング
『トイレットトレーニング』より : トイレットトレーニングとは、排泄に絡む便所の使用に関する訓練を言う行為。主に家庭内で最も基本的な躾として行われる。
人間の幼児の場合には、おむつの取れた後、一般の便所 トイレで用が足せるようにすることがトイレットトレーニングである。お尻のしつけとも言う。
排泄の間隔が2〜3時間おきになって、一人歩きができる様になっていく年齢から開始される物である。
お座りができるようになれば、おまるに座らせて排泄させることも不可能ではないが、早くからトイレでできるできないは赤ん坊によって能力、個人差が大きく、一旦トレーニングに成功したとしても逆戻りすることが少なくない(オムツの節約にはなるが)。
トイレタリー
トイレタリー(英:toiletry)とは、身体の洗浄や身嗜み、嗜好などを目的とした商品の総称。
トイレタリーとは日用品の一ジャンルであり、広義には化学薬品、細分化すると化粧品や洗剤、医薬品(医薬部外品)などに含まれる。だが、いずれに分類してもイメージなどに問題が生じることから、便宜上分類されるカテゴリと見做してよい。なお、日本語では適切な表現が見あたらないため、日常生活や業界でもトイレタリーという用語を用いることが多い。だが、英語でtoiletryとは化粧品のことであるため、和製英語となっている部分もある。
ただし、業界でもトイレタリーの定義は曖昧で、文献によっては住居用や台所用、衣類用といった洗剤を含める場合もある。しかし、トイレタリーとは本来、身嗜みのための商品であるので、ここでは洗剤は含めないことにした。(洗剤の項を参照)。もっとも、一般に洗剤・トイレタリー業界と一括りで呼ばれることがあるのは、トイレタリーを製造している業界は洗剤を製造している企業の分野拡大が目立つからである。
トイレットペーパー
トイレットペーパーとは、便所で用を足す際に後始末に用いられる紙。普通巻紙(ロール紙)になっているので、トイレットロールとも呼ぶ。
日本ではどれもほぼ一定の大きさであって、便所の各個室備え付けのホルダーにとりつけてある。国によってはロールがかなり大きく、その場合はホルダーもそれに対応したものとなっている。また、これが個室の入口に設置され、必要分を取ってから個室に入るようになっている場合もある。
各国の紙資源の状況、下水道の状況により、用いられている紙は違いがある。一般的には柔らかい紙が使われるが、硬い紙が一般的に用いられている場合には同時に処理せず、別に汚物入れに捨てるように指示されている。
トイレットティシュー
『トイレットペーパー』より : トイレットペーパーとは、便所で用を足す際に後始末に用いられる紙。普通巻紙(ロール紙)になっているので、トイレットロールとも呼ぶ。
日本ではどれもほぼ一定の大きさであって、便所の各個室備え付けのホルダーにとりつけてある。国によってはロールがかなり大きく、その場合はホルダーもそれに対応したものとなっている。また、これが個室の入口に設置され、必要分を取ってから個室に入るようになっている場合もある。
各国の紙資源の状況、下水道の状況により、用いられている紙は違いがある。一般的には柔らかい紙が使われるが、硬い紙が一般的に用いられている場合には同時に処理せず、別に汚物入れに捨てるように指示されている。
トイレの花子さん
トイレの花子さん(トイレのはなこさん)は学校のトイレに住んでいると言われるオバケ。一種の都市伝説である。
学校の特定のトイレに特定の方法で呼びかけると、誰もいないはずのトイレから返事があるといった話が基本パターン。細かい内容は噂される学校ごとに異なる。赤いスカートをはいた、おかっぱ頭の女の子の姿が有名となっている。
かつては三番目の花子さんと呼ばれ、古くは1950年頃から存在していた都市伝説。1980年代頃から全国の子供たちの間で噂になり、1990年代には映画、アニメなど、様々な作品の題材になった。
話の出所としては、一人の学校好きの少女が学校内にある奥から三番目のトイレに隠れ、発狂した母親により殺害されたとする話が元になったとされる。
トイレット博士
『トイレット博士』(トイレットはかせ)は、とりいかずよしにより昭和45年から昭和52年まで週刊少年ジャンプ誌上に連載されたギャグ漫画作品。
当時の少年誌としては過激な性表現・暴力表現で物議を醸し、社会現象になった。
とりいかずよしの出世作であり代表作の一つ。便宜上、内容にて大きく分けて3部になる。
「トイレット博士」は、7年間に渡り少年ジャンプに連載され、ジャンプを数百万部雑誌にのし上げた立て役者にもなった、大ヒット作品である。
「トイレット〜」と聞いて一般的に連想されるイメージは、大方「メタクソ団」、「マタンキ」、「天怒りて非道を断つ! 臨、兵、闘、者、皆、陳、烈、在、前、七年ゴロシ〜!」などの、ジャンプの看板マンガとしてブレイクしてからの、後期の作品群からのものだろう。
トイレの使用を予約するシステム及び方法の特許
トイレの使用を予約するシステム及び方法(System and method for providing reservations for restroom use)の特許(米国特許第6,329,919号)は、IBMがアメリカ合衆国 米国において2000年8月14日に出願し、2001年12月11日に認められた特許。
請求項の数は64。IBMが特許維持料を納付しなかったため2002年10月に権利が消滅した。なお、日本、欧州などの米国以外の国・地域では、この発明は出願されていない。
名称:System and method for providing reservations for restroom use
出願日:2000年8月14日
出願番号:09/639,254
特許日:2001年12月11日
特許番号:6,329,919
この発明については、日本の特許庁や欧州特許庁では特許が認められる可能性が低いと考えられることから、アメリカ合衆国特許商標庁 米国特許商標庁の審査の質が低いことを示す一つの例とされる。同様の特許の例としては以下のものが有名である。
『便所』より : 便所(べんじょ、英”Toilet”)とは、大小便など排泄の用を足すするための設備を備えている場所。様々な呼称がある。呼称に関しては後述の便所#呼称について 呼称についてを参照されたし。
この施設は、悪臭を放ち周辺の環境を汚損するおそれのある汚物(主に糞・尿・嘔吐 吐瀉物)を衛生的に処分するための機能を持っている。近年の文明社会の多くでは、これら施設の多くは水洗(水の流れる力を用いて、強制的に汚物を流し去る)の物が見られるが、宇宙船の中では乾燥させたりするものもあり、1970年の日本万国博覧会 大阪万博では都市ガス ガスによる燃焼方式も見られるなど、衛生的に処理できれば、特にその方法は問わない。乾燥地帯では砂を掛けて糞便を乾燥させて処分する様式も見られる。(水洗便器の詳細は便器が詳しい)
トイレット
『便所』より : 便所(べんじょ、英”Toilet”)とは、大小便など排泄の用を足すするための設備を備えている場所。様々な呼称がある。呼称に関しては後述の便所#呼称について 呼称についてを参照されたし。
この施設は、悪臭を放ち周辺の環境を汚損するおそれのある汚物(主に糞・尿・嘔吐 吐瀉物)を衛生的に処分するための機能を持っている。近年の文明社会の多くでは、これら施設の多くは水洗(水の流れる力を用いて、強制的に汚物を流し去る)の物が見られるが、宇宙船の中では乾燥させたりするものもあり、1970年の日本万国博覧会 大阪万博では都市ガス ガスによる燃焼方式も見られるなど、衛生的に処理できれば、特にその方法は問わない。乾燥地帯では砂を掛けて糞便を乾燥させて処分する様式も見られる。(水洗便器の詳細は便器が詳しい)
トイレットトレーニング
トイレットトレーニングとは、排泄に絡む便所の使用に関する訓練を言う行為。主に家庭内で最も基本的な躾として行われる。
人間の幼児の場合には、おむつの取れた後、一般の便所 トイレで用が足せるようにすることがトイレットトレーニングである。お尻のしつけとも言う。
排泄の間隔が2〜3時間おきになって、一人歩きができる様になっていく年齢から開始される物である。
お座りができるようになれば、おまるに座らせて排泄させることも不可能ではないが、早くからトイレでできるできないは赤ん坊によって能力、個人差が大きく、一旦トレーニングに成功したとしても逆戻りすることが少なくない(オムツの節約にはなるが)。
トイレトレーニング
『トイレットトレーニング』より : トイレットトレーニングとは、排泄に絡む便所の使用に関する訓練を言う行為。主に家庭内で最も基本的な躾として行われる。
人間の幼児の場合には、おむつの取れた後、一般の便所 トイレで用が足せるようにすることがトイレットトレーニングである。お尻のしつけとも言う。
排泄の間隔が2〜3時間おきになって、一人歩きができる様になっていく年齢から開始される物である。
お座りができるようになれば、おまるに座らせて排泄させることも不可能ではないが、早くからトイレでできるできないは赤ん坊によって能力、個人差が大きく、一旦トレーニングに成功したとしても逆戻りすることが少なくない(オムツの節約にはなるが)。
トイレタリー
トイレタリー(英:toiletry)とは、身体の洗浄や身嗜み、嗜好などを目的とした商品の総称。
トイレタリーとは日用品の一ジャンルであり、広義には化学薬品、細分化すると化粧品や洗剤、医薬品(医薬部外品)などに含まれる。だが、いずれに分類してもイメージなどに問題が生じることから、便宜上分類されるカテゴリと見做してよい。なお、日本語では適切な表現が見あたらないため、日常生活や業界でもトイレタリーという用語を用いることが多い。だが、英語でtoiletryとは化粧品のことであるため、和製英語となっている部分もある。
ただし、業界でもトイレタリーの定義は曖昧で、文献によっては住居用や台所用、衣類用といった洗剤を含める場合もある。しかし、トイレタリーとは本来、身嗜みのための商品であるので、ここでは洗剤は含めないことにした。(洗剤の項を参照)。もっとも、一般に洗剤・トイレタリー業界と一括りで呼ばれることがあるのは、トイレタリーを製造している業界は洗剤を製造している企業の分野拡大が目立つからである。
トイレットペーパー
トイレットペーパーとは、便所で用を足す際に後始末に用いられる紙。普通巻紙(ロール紙)になっているので、トイレットロールとも呼ぶ。
日本ではどれもほぼ一定の大きさであって、便所の各個室備え付けのホルダーにとりつけてある。国によってはロールがかなり大きく、その場合はホルダーもそれに対応したものとなっている。また、これが個室の入口に設置され、必要分を取ってから個室に入るようになっている場合もある。
各国の紙資源の状況、下水道の状況により、用いられている紙は違いがある。一般的には柔らかい紙が使われるが、硬い紙が一般的に用いられている場合には同時に処理せず、別に汚物入れに捨てるように指示されている。
トイレットティシュー
『トイレットペーパー』より : トイレットペーパーとは、便所で用を足す際に後始末に用いられる紙。普通巻紙(ロール紙)になっているので、トイレットロールとも呼ぶ。
日本ではどれもほぼ一定の大きさであって、便所の各個室備え付けのホルダーにとりつけてある。国によってはロールがかなり大きく、その場合はホルダーもそれに対応したものとなっている。また、これが個室の入口に設置され、必要分を取ってから個室に入るようになっている場合もある。
各国の紙資源の状況、下水道の状況により、用いられている紙は違いがある。一般的には柔らかい紙が使われるが、硬い紙が一般的に用いられている場合には同時に処理せず、別に汚物入れに捨てるように指示されている。
トイレの花子さん
トイレの花子さん(トイレのはなこさん)は学校のトイレに住んでいると言われるオバケ。一種の都市伝説である。
学校の特定のトイレに特定の方法で呼びかけると、誰もいないはずのトイレから返事があるといった話が基本パターン。細かい内容は噂される学校ごとに異なる。赤いスカートをはいた、おかっぱ頭の女の子の姿が有名となっている。
かつては三番目の花子さんと呼ばれ、古くは1950年頃から存在していた都市伝説。1980年代頃から全国の子供たちの間で噂になり、1990年代には映画、アニメなど、様々な作品の題材になった。
話の出所としては、一人の学校好きの少女が学校内にある奥から三番目のトイレに隠れ、発狂した母親により殺害されたとする話が元になったとされる。
トイレット博士
『トイレット博士』(トイレットはかせ)は、とりいかずよしにより昭和45年から昭和52年まで週刊少年ジャンプ誌上に連載されたギャグ漫画作品。
当時の少年誌としては過激な性表現・暴力表現で物議を醸し、社会現象になった。
とりいかずよしの出世作であり代表作の一つ。便宜上、内容にて大きく分けて3部になる。
「トイレット博士」は、7年間に渡り少年ジャンプに連載され、ジャンプを数百万部雑誌にのし上げた立て役者にもなった、大ヒット作品である。
「トイレット〜」と聞いて一般的に連想されるイメージは、大方「メタクソ団」、「マタンキ」、「天怒りて非道を断つ! 臨、兵、闘、者、皆、陳、烈、在、前、七年ゴロシ〜!」などの、ジャンプの看板マンガとしてブレイクしてからの、後期の作品群からのものだろう。
トイレの使用を予約するシステム及び方法の特許
トイレの使用を予約するシステム及び方法(System and method for providing reservations for restroom use)の特許(米国特許第6,329,919号)は、IBMがアメリカ合衆国 米国において2000年8月14日に出願し、2001年12月11日に認められた特許。
請求項の数は64。IBMが特許維持料を納付しなかったため2002年10月に権利が消滅した。なお、日本、欧州などの米国以外の国・地域では、この発明は出願されていない。
名称:System and method for providing reservations for restroom use
出願日:2000年8月14日
出願番号:09/639,254
特許日:2001年12月11日
特許番号:6,329,919
この発明については、日本の特許庁や欧州特許庁では特許が認められる可能性が低いと考えられることから、アメリカ合衆国特許商標庁 米国特許商標庁の審査の質が低いことを示す一つの例とされる。同様の特許の例としては以下のものが有名である。