スポンサードリンク
訪問介護をまるごと検索
訪問介護を詳しく調べる
訪問介護でお困りなら、ご確認してみてください。
お近くのバリアフリー(介護)リフォーム業者から
無料見積もりをお取り寄せして比較できます。
忙しいあなたにも手間なく、
ご自分の目線で、信頼の出来る工務店や
リフォーム業者をお選びいただき、
安心のリフォーム工事を行っていただければと思います。
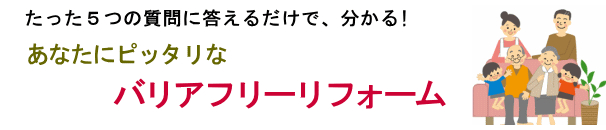
訪問介護の関連情報
訪問介護とは?
訪問介護
訪問介護(ほうもんかいご)とは、介護保険法第7条の6において「要介護者又は要支援者であって、居宅(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるものについて、その者の居宅において介護福祉士その他厚生労働省令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの」と定義されている。
上記の訪問介護を指してホームヘルプサービスと呼称することもある。しかし、広義には、介護保険法以外の法令(たとえば障害者自立支援法など)に基づくサービスや法令に基づかない私的なサービスが含まれることもある。
訪問介護員
訪問介護員(ほうもんかいごいん、英語 英Home Helper)は、訪問介護を行う者の資格の一つで、都道府県知事の指定する訪問介護員養成研修の課程を修了した者をいう。介護保険法第7条の6において「その他厚生労働省令で定める者」とされており、介護保険法施行令に定められている。かつては家庭奉仕員と呼ばれ、現在は一般にホームヘルパーと呼ばれている。
厚生労働省は2005年、介護に携わる者の資格を介護福祉士に一本化する方向を打ち出したが、需要に対し供給が全く追いついていない状況であり、2級以上のホームヘルパーの需要は依然として高い状況にある。
課程 研修内容 受講対象者 時間
訪問介護(ほうもんかいご)とは、介護保険法第7条の6において「要介護者又は要支援者であって、居宅(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホームその他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるものについて、その者の居宅において介護福祉士その他厚生労働省令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの」と定義されている。
上記の訪問介護を指してホームヘルプサービスと呼称することもある。しかし、広義には、介護保険法以外の法令(たとえば障害者自立支援法など)に基づくサービスや法令に基づかない私的なサービスが含まれることもある。
訪問介護員
訪問介護員(ほうもんかいごいん、英語 英Home Helper)は、訪問介護を行う者の資格の一つで、都道府県知事の指定する訪問介護員養成研修の課程を修了した者をいう。介護保険法第7条の6において「その他厚生労働省令で定める者」とされており、介護保険法施行令に定められている。かつては家庭奉仕員と呼ばれ、現在は一般にホームヘルパーと呼ばれている。
厚生労働省は2005年、介護に携わる者の資格を介護福祉士に一本化する方向を打ち出したが、需要に対し供給が全く追いついていない状況であり、2級以上のホームヘルパーの需要は依然として高い状況にある。
課程 研修内容 受講対象者 時間