スポンサードリンク
福祉をまるごと検索
福祉を詳しく調べる
福祉でお困りなら、ご確認してみてください。
お近くのバリアフリー(介護)リフォーム業者から
無料見積もりをお取り寄せして比較できます。
忙しいあなたにも手間なく、
ご自分の目線で、信頼の出来る工務店や
リフォーム業者をお選びいただき、
安心のリフォーム工事を行っていただければと思います。
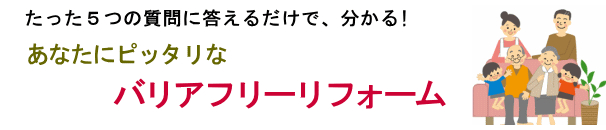
福祉の関連情報
福祉とは?
福祉
福祉(ふくし)とは、「しあわせ」や「ゆたかさ」を意味する言葉で、広義で「公共の福祉」などと使われる。
社会福祉(social-welfare)は、未成年者、高齢者や障害者で生活上なんらかの支援や介助を必要とする人、経済的困窮者・ホームレスなどに対し、生活の質を維持・向上させるためのサービスを社会的に提供すること、あるいはそのための制度や設備を整備することを指す。
狭義で所得保障制度などの社会保障を指す。さらに、狭義には生活保護法や児童福祉法、身体障害者福祉法など社会保障の一分野(社会福祉制度とそれに基づいたサービス・事業)を指す。
社会福祉制度とは、社会福祉に関する制度。
社会福祉政策とは、政府による、社会福祉サービスの運営や提供に関するプログラム。
福祉国家論
福祉国家論(ふくしこっかろん 英:Welfare State)は、国家の機能を安全保障や治安維持などだけでなく、経済的格差の是正のための社会保障制度の整備や財政政策、雇用政策も推進して、福祉国家を目指すべきとする考え方。福祉国家の対義語で、戦争国家(英:Warfare State)などがある。ともに第二次世界大戦でイギリスが連合国を福祉国家、枢軸国を戦争国家と政治宣伝したのが始まり。
石油ショック以後、社会保障の為の国家支出による財政の圧迫、あるいはそれまで取られてきた国営企業の非効率性(イギリス)、労使協調体制の後退(ドイツにおけるコーポラティズム)等による経済閉塞化が問題となった。その結果として福祉国家の行き詰まりが指摘され始め、新自由主義の台頭などにより、福祉国家を巡る議論は全否定もしくは礼賛のどちらかとなり、混乱をきたす。1990年にエスピン・アンデルセンが福祉国家に変わる新しい概念として福祉レジーム論を提起し、経済レジームとの連関でグローバル化への対応の多様性を論じた。
福祉国家
『福祉国家論』より : 福祉国家論(ふくしこっかろん 英:Welfare State)は、国家の機能を安全保障や治安維持などだけでなく、経済的格差の是正のための社会保障制度の整備や財政政策、雇用政策も推進して、福祉国家を目指すべきとする考え方。福祉国家の対義語で、戦争国家(英:Warfare State)などがある。ともに第二次世界大戦でイギリスが連合国を福祉国家、枢軸国を戦争国家と政治宣伝したのが始まり。
石油ショック以後、社会保障の為の国家支出による財政の圧迫、あるいはそれまで取られてきた国営企業の非効率性(イギリス)、労使協調体制の後退(ドイツにおけるコーポラティズム)等による経済閉塞化が問題となった。その結果として福祉国家の行き詰まりが指摘され始め、新自由主義の台頭などにより、福祉国家を巡る議論は全否定もしくは礼賛のどちらかとなり、混乱をきたす。1990年にエスピン・アンデルセンが福祉国家に変わる新しい概念として福祉レジーム論を提起し、経済レジームとの連関でグローバル化への対応の多様性を論じた。
福祉レジーム
『福祉国家論』より : 福祉国家論(ふくしこっかろん 英:Welfare State)は、国家の機能を安全保障や治安維持などだけでなく、経済的格差の是正のための社会保障制度の整備や財政政策、雇用政策も推進して、福祉国家を目指すべきとする考え方。福祉国家の対義語で、戦争国家(英:Warfare State)などがある。ともに第二次世界大戦でイギリスが連合国を福祉国家、枢軸国を戦争国家と政治宣伝したのが始まり。
石油ショック以後、社会保障の為の国家支出による財政の圧迫、あるいはそれまで取られてきた国営企業の非効率性(イギリス)、労使協調体制の後退(ドイツにおけるコーポラティズム)等による経済閉塞化が問題となった。その結果として福祉国家の行き詰まりが指摘され始め、新自由主義の台頭などにより、福祉国家を巡る議論は全否定もしくは礼賛のどちらかとなり、混乱をきたす。1990年にエスピン・アンデルセンが福祉国家に変わる新しい概念として福祉レジーム論を提起し、経済レジームとの連関でグローバル化への対応の多様性を論じた。
福祉レジーム論
『福祉国家論』より : 福祉国家論(ふくしこっかろん 英:Welfare State)は、国家の機能を安全保障や治安維持などだけでなく、経済的格差の是正のための社会保障制度の整備や財政政策、雇用政策も推進して、福祉国家を目指すべきとする考え方。福祉国家の対義語で、戦争国家(英:Warfare State)などがある。ともに第二次世界大戦でイギリスが連合国を福祉国家、枢軸国を戦争国家と政治宣伝したのが始まり。
石油ショック以後、社会保障の為の国家支出による財政の圧迫、あるいはそれまで取られてきた国営企業の非効率性(イギリス)、労使協調体制の後退(ドイツにおけるコーポラティズム)等による経済閉塞化が問題となった。その結果として福祉国家の行き詰まりが指摘され始め、新自由主義の台頭などにより、福祉国家を巡る議論は全否定もしくは礼賛のどちらかとなり、混乱をきたす。1990年にエスピン・アンデルセンが福祉国家に変わる新しい概念として福祉レジーム論を提起し、経済レジームとの連関でグローバル化への対応の多様性を論じた。
福祉法令一覧
福祉法令一覧(ふくしほうれいいちらん)は、各種福祉関連法律について紹介する。
介護保険法
健康保険法
国民健康保険法
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
児童虐待の防止等に関する法律
児童福祉法
社会福祉法
社会福祉士及び介護福祉士法
社会保険診療報酬支払基金法
社会保険労務士法
障害者基本法
障害者自立支援法
障害者の雇用の促進等に関する法律
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
身体障害者福祉法
身体障害者補助犬法
生活保護法
福祉学部
『社会福祉学部』より : 社会福祉学部(しゃかいふくしがくぶ)は大学において社会福祉学を中心とした教育が行われる学部であり、現在(2005年)全国に33存在する。
主に社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保育士などの福祉施設における専門職を養成するための教育が行われている。1960年代から始まる障害者の社会運動の広がりと人口の高齢化を受け、福祉専門職の養成が社会の急務となった。そのため、全国の私立大学がリードをとり、急速に設置を広めていった学部である。
なお、現在では「学部」として独立しているものも増えてきているが、一方で他の学部(社会学部や文学部)の「社会福祉学科」や「社会福祉コース」などの位置づけが続けられている大学も多く残っている。また、学部の名称を「総合福祉学部」や「現代福祉学部」「健康福祉学部」「人間福祉学部」などとしている大学もあり、多様である。さらには、国立大学法人による大学(旧・国立大学)の教育学部などでは、教員採用の現状の厳しさも考慮して「教育福祉科学部」などへ改組を行ったり、また「教育学部」の名称は継続しながらも内部で福祉関係の国家資格の取得課程を設けているところも登場してきている。
福祉総合学部
『社会福祉学部』より : 社会福祉学部(しゃかいふくしがくぶ)は大学において社会福祉学を中心とした教育が行われる学部であり、現在(2005年)全国に33存在する。
主に社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保育士などの福祉施設における専門職を養成するための教育が行われている。1960年代から始まる障害者の社会運動の広がりと人口の高齢化を受け、福祉専門職の養成が社会の急務となった。そのため、全国の私立大学がリードをとり、急速に設置を広めていった学部である。
なお、現在では「学部」として独立しているものも増えてきているが、一方で他の学部(社会学部や文学部)の「社会福祉学科」や「社会福祉コース」などの位置づけが続けられている大学も多く残っている。また、学部の名称を「総合福祉学部」や「現代福祉学部」「健康福祉学部」「人間福祉学部」などとしている大学もあり、多様である。さらには、国立大学法人による大学(旧・国立大学)の教育学部などでは、教員採用の現状の厳しさも考慮して「教育福祉科学部」などへ改組を行ったり、また「教育学部」の名称は継続しながらも内部で福祉関係の国家資格の取得課程を設けているところも登場してきている。
福祉ネットワーク
福祉ネットワーク(ふくしねっとわーく)は、日本放送協会 NHK教育テレビで平日(月〜木曜)の20:00~20:30(再放送は翌週の同じ曜日13:20~13:50)放送中の情報番組である。
以前からNHK教育テレビでは毎週1回の番組「あすの福祉」を長年放送してきたが、これを2000年度から帯番組「にんげんゆうゆう」としてリニューアルし、毎週あるテーマを決めて高齢者、身体障害者の福祉活動や小児育児の問題にも鋭いメスを入れて展開するようになった。
現タイトルになった2003年度からは日替わりでジャンルを特定し、更に毎月一つのテーマを決めてきめ細かい福祉情報を届けている。(文字多重放送による字幕放送を実施中。なお火曜日は週によって字幕が入らない場合がある。また月曜日は不定期で視覚障害者・中途失明者を題材にした番組も放送されるため、その場合は解説放送を行うこともある)
福祉資格等一覧
福祉資格等一覧(ふくししかくなどいちらん)
【知的障害者福祉法】
知的障害者福祉司
【児童福祉法】
児童福祉司
保育士
【身体障害者福祉法】
身体障害者福祉司
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】
環境衛生指導員
環境衛生監視員
【有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(家庭用品規制法)】
家庭用品衛生監視員
【社会福祉士及び介護福祉士法】
社会福祉士
福祉(ふくし)とは、「しあわせ」や「ゆたかさ」を意味する言葉で、広義で「公共の福祉」などと使われる。
社会福祉(social-welfare)は、未成年者、高齢者や障害者で生活上なんらかの支援や介助を必要とする人、経済的困窮者・ホームレスなどに対し、生活の質を維持・向上させるためのサービスを社会的に提供すること、あるいはそのための制度や設備を整備することを指す。
狭義で所得保障制度などの社会保障を指す。さらに、狭義には生活保護法や児童福祉法、身体障害者福祉法など社会保障の一分野(社会福祉制度とそれに基づいたサービス・事業)を指す。
社会福祉制度とは、社会福祉に関する制度。
社会福祉政策とは、政府による、社会福祉サービスの運営や提供に関するプログラム。
福祉国家論
福祉国家論(ふくしこっかろん 英:Welfare State)は、国家の機能を安全保障や治安維持などだけでなく、経済的格差の是正のための社会保障制度の整備や財政政策、雇用政策も推進して、福祉国家を目指すべきとする考え方。福祉国家の対義語で、戦争国家(英:Warfare State)などがある。ともに第二次世界大戦でイギリスが連合国を福祉国家、枢軸国を戦争国家と政治宣伝したのが始まり。
石油ショック以後、社会保障の為の国家支出による財政の圧迫、あるいはそれまで取られてきた国営企業の非効率性(イギリス)、労使協調体制の後退(ドイツにおけるコーポラティズム)等による経済閉塞化が問題となった。その結果として福祉国家の行き詰まりが指摘され始め、新自由主義の台頭などにより、福祉国家を巡る議論は全否定もしくは礼賛のどちらかとなり、混乱をきたす。1990年にエスピン・アンデルセンが福祉国家に変わる新しい概念として福祉レジーム論を提起し、経済レジームとの連関でグローバル化への対応の多様性を論じた。
福祉国家
『福祉国家論』より : 福祉国家論(ふくしこっかろん 英:Welfare State)は、国家の機能を安全保障や治安維持などだけでなく、経済的格差の是正のための社会保障制度の整備や財政政策、雇用政策も推進して、福祉国家を目指すべきとする考え方。福祉国家の対義語で、戦争国家(英:Warfare State)などがある。ともに第二次世界大戦でイギリスが連合国を福祉国家、枢軸国を戦争国家と政治宣伝したのが始まり。
石油ショック以後、社会保障の為の国家支出による財政の圧迫、あるいはそれまで取られてきた国営企業の非効率性(イギリス)、労使協調体制の後退(ドイツにおけるコーポラティズム)等による経済閉塞化が問題となった。その結果として福祉国家の行き詰まりが指摘され始め、新自由主義の台頭などにより、福祉国家を巡る議論は全否定もしくは礼賛のどちらかとなり、混乱をきたす。1990年にエスピン・アンデルセンが福祉国家に変わる新しい概念として福祉レジーム論を提起し、経済レジームとの連関でグローバル化への対応の多様性を論じた。
福祉レジーム
『福祉国家論』より : 福祉国家論(ふくしこっかろん 英:Welfare State)は、国家の機能を安全保障や治安維持などだけでなく、経済的格差の是正のための社会保障制度の整備や財政政策、雇用政策も推進して、福祉国家を目指すべきとする考え方。福祉国家の対義語で、戦争国家(英:Warfare State)などがある。ともに第二次世界大戦でイギリスが連合国を福祉国家、枢軸国を戦争国家と政治宣伝したのが始まり。
石油ショック以後、社会保障の為の国家支出による財政の圧迫、あるいはそれまで取られてきた国営企業の非効率性(イギリス)、労使協調体制の後退(ドイツにおけるコーポラティズム)等による経済閉塞化が問題となった。その結果として福祉国家の行き詰まりが指摘され始め、新自由主義の台頭などにより、福祉国家を巡る議論は全否定もしくは礼賛のどちらかとなり、混乱をきたす。1990年にエスピン・アンデルセンが福祉国家に変わる新しい概念として福祉レジーム論を提起し、経済レジームとの連関でグローバル化への対応の多様性を論じた。
福祉レジーム論
『福祉国家論』より : 福祉国家論(ふくしこっかろん 英:Welfare State)は、国家の機能を安全保障や治安維持などだけでなく、経済的格差の是正のための社会保障制度の整備や財政政策、雇用政策も推進して、福祉国家を目指すべきとする考え方。福祉国家の対義語で、戦争国家(英:Warfare State)などがある。ともに第二次世界大戦でイギリスが連合国を福祉国家、枢軸国を戦争国家と政治宣伝したのが始まり。
石油ショック以後、社会保障の為の国家支出による財政の圧迫、あるいはそれまで取られてきた国営企業の非効率性(イギリス)、労使協調体制の後退(ドイツにおけるコーポラティズム)等による経済閉塞化が問題となった。その結果として福祉国家の行き詰まりが指摘され始め、新自由主義の台頭などにより、福祉国家を巡る議論は全否定もしくは礼賛のどちらかとなり、混乱をきたす。1990年にエスピン・アンデルセンが福祉国家に変わる新しい概念として福祉レジーム論を提起し、経済レジームとの連関でグローバル化への対応の多様性を論じた。
福祉法令一覧
福祉法令一覧(ふくしほうれいいちらん)は、各種福祉関連法律について紹介する。
介護保険法
健康保険法
国民健康保険法
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
児童虐待の防止等に関する法律
児童福祉法
社会福祉法
社会福祉士及び介護福祉士法
社会保険診療報酬支払基金法
社会保険労務士法
障害者基本法
障害者自立支援法
障害者の雇用の促進等に関する法律
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
身体障害者福祉法
身体障害者補助犬法
生活保護法
福祉学部
『社会福祉学部』より : 社会福祉学部(しゃかいふくしがくぶ)は大学において社会福祉学を中心とした教育が行われる学部であり、現在(2005年)全国に33存在する。
主に社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保育士などの福祉施設における専門職を養成するための教育が行われている。1960年代から始まる障害者の社会運動の広がりと人口の高齢化を受け、福祉専門職の養成が社会の急務となった。そのため、全国の私立大学がリードをとり、急速に設置を広めていった学部である。
なお、現在では「学部」として独立しているものも増えてきているが、一方で他の学部(社会学部や文学部)の「社会福祉学科」や「社会福祉コース」などの位置づけが続けられている大学も多く残っている。また、学部の名称を「総合福祉学部」や「現代福祉学部」「健康福祉学部」「人間福祉学部」などとしている大学もあり、多様である。さらには、国立大学法人による大学(旧・国立大学)の教育学部などでは、教員採用の現状の厳しさも考慮して「教育福祉科学部」などへ改組を行ったり、また「教育学部」の名称は継続しながらも内部で福祉関係の国家資格の取得課程を設けているところも登場してきている。
福祉総合学部
『社会福祉学部』より : 社会福祉学部(しゃかいふくしがくぶ)は大学において社会福祉学を中心とした教育が行われる学部であり、現在(2005年)全国に33存在する。
主に社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、保育士などの福祉施設における専門職を養成するための教育が行われている。1960年代から始まる障害者の社会運動の広がりと人口の高齢化を受け、福祉専門職の養成が社会の急務となった。そのため、全国の私立大学がリードをとり、急速に設置を広めていった学部である。
なお、現在では「学部」として独立しているものも増えてきているが、一方で他の学部(社会学部や文学部)の「社会福祉学科」や「社会福祉コース」などの位置づけが続けられている大学も多く残っている。また、学部の名称を「総合福祉学部」や「現代福祉学部」「健康福祉学部」「人間福祉学部」などとしている大学もあり、多様である。さらには、国立大学法人による大学(旧・国立大学)の教育学部などでは、教員採用の現状の厳しさも考慮して「教育福祉科学部」などへ改組を行ったり、また「教育学部」の名称は継続しながらも内部で福祉関係の国家資格の取得課程を設けているところも登場してきている。
福祉ネットワーク
福祉ネットワーク(ふくしねっとわーく)は、日本放送協会 NHK教育テレビで平日(月〜木曜)の20:00~20:30(再放送は翌週の同じ曜日13:20~13:50)放送中の情報番組である。
以前からNHK教育テレビでは毎週1回の番組「あすの福祉」を長年放送してきたが、これを2000年度から帯番組「にんげんゆうゆう」としてリニューアルし、毎週あるテーマを決めて高齢者、身体障害者の福祉活動や小児育児の問題にも鋭いメスを入れて展開するようになった。
現タイトルになった2003年度からは日替わりでジャンルを特定し、更に毎月一つのテーマを決めてきめ細かい福祉情報を届けている。(文字多重放送による字幕放送を実施中。なお火曜日は週によって字幕が入らない場合がある。また月曜日は不定期で視覚障害者・中途失明者を題材にした番組も放送されるため、その場合は解説放送を行うこともある)
福祉資格等一覧
福祉資格等一覧(ふくししかくなどいちらん)
【知的障害者福祉法】
知的障害者福祉司
【児童福祉法】
児童福祉司
保育士
【身体障害者福祉法】
身体障害者福祉司
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】
環境衛生指導員
環境衛生監視員
【有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(家庭用品規制法)】
家庭用品衛生監視員
【社会福祉士及び介護福祉士法】
社会福祉士