スポンサードリンク
社会保障をまるごと検索
社会保障を詳しく調べる
社会保障でお困りなら、ご確認してみてください。
お近くのバリアフリー(介護)リフォーム業者から
無料見積もりをお取り寄せして比較できます。
忙しいあなたにも手間なく、
ご自分の目線で、信頼の出来る工務店や
リフォーム業者をお選びいただき、
安心のリフォーム工事を行っていただければと思います。
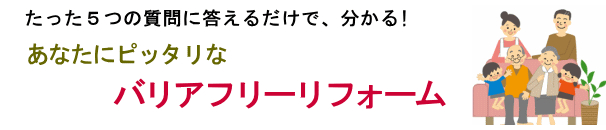
社会保障の関連情報
社会保障とは?
社会保障
社会保障(しゃかいほしょう、social security)とは、本来は個人的リスクである、病気・けが・出産・障害・死亡・加齢・失業などの生活上の問題について貧困を予防し、貧困者を救い、生活を安定させるために国家または社会が所得移転によって所得を保障し、医療や介護などの社会サービスを給付すること、またはその制度を指す。
社会保障の歴史は、経済社会の動きと密接に関係しており、社会保障の仕組みは、各国が長い歴史の中で、相互に影響を与えながら積み重ねてきたものである。19世紀から20世紀にかけては、各国で失業問題が最大の課題であり、その中から社会保障が進展してきた。また、本来、福祉とは正反対の戦争が契機となって社会保障の基礎がスタートした。20世紀後半以降、先進各国では経済の低成長・少子・高齢化が社会保障の大きな課題である。
社会保障制度
『社会保障』より : 社会保障(しゃかいほしょう、social security)とは、本来は個人的リスクである、老齢・病気・失業・障害などの生活上の問題について、貧困の予防や生活の安定などのため、社会的に所得移転を行い所得や医療を保障、社会サービスを給付すること、またはその制度を指す。
社会が封建制から資本主義に移行する頃、イギリスでは救貧法をつくり、働く能力はあるが働かない窮民を救済したのが制度的な始まりと言われているが、当時社会保障という言葉はなかった。
資本主義が定着していくと資本家から、失業は個人の問題であり、国による貧民救済は有害との主張がなされた。ドイツでは、防貧のために労働者が自分たちの賃金の一部を出し合って助け合う共済組合を作ったが、不況や失業による貧困が深刻すぎ全ての人を救済しきれなかった。そこで労働者は生活保障を国と資本家で行うよう主張した。結果として1883年ドイツで初めて国の制度として社会保険が実現した。社会保険制度を創設しつつ社会主義運動を弾圧する鉄血宰相オットー・フォン・ビスマルクの政策は「飴とムチ」の政策と呼ばれる。このとき保険料には、労働者だけでなく、雇用主や国の負担が導入された。このドイツの社会保険制度は、その後の福祉国家のモデルのひとつになっていく。
社会保障法
社会保障法(しゃかいほしょうほう)とは、保障の必要な者に対して、日本国 国や地方公共団体などが行う給付行政 給付行為をめぐる権利・義務を中心として、その費用負担を定めた、社会保障に関する法 (法学) 法の総称である。
広義には、公的扶助や社会保険をはじめ、環境衛生や恩給なども含む。通常は狭義に解し、社会手当や福祉 社会福祉を主要な柱としている。
社会保障に関する法としては、公的扶助関連では生活保護法や児童扶養手当法などがあり、社会保険関連では、健康保険法や国民年金法、雇用保険法など、数多くの法律がある。
アメリカ合衆国においては、1935年にニューディール政策の一環として制定されている。
社会保険制度、公的扶助、社会福祉事業の3つを骨格とし、管轄機関として社会保障局が設置されている。
社会保障(しゃかいほしょう、social security)とは、本来は個人的リスクである、病気・けが・出産・障害・死亡・加齢・失業などの生活上の問題について貧困を予防し、貧困者を救い、生活を安定させるために国家または社会が所得移転によって所得を保障し、医療や介護などの社会サービスを給付すること、またはその制度を指す。
社会保障の歴史は、経済社会の動きと密接に関係しており、社会保障の仕組みは、各国が長い歴史の中で、相互に影響を与えながら積み重ねてきたものである。19世紀から20世紀にかけては、各国で失業問題が最大の課題であり、その中から社会保障が進展してきた。また、本来、福祉とは正反対の戦争が契機となって社会保障の基礎がスタートした。20世紀後半以降、先進各国では経済の低成長・少子・高齢化が社会保障の大きな課題である。
社会保障制度
『社会保障』より : 社会保障(しゃかいほしょう、social security)とは、本来は個人的リスクである、老齢・病気・失業・障害などの生活上の問題について、貧困の予防や生活の安定などのため、社会的に所得移転を行い所得や医療を保障、社会サービスを給付すること、またはその制度を指す。
社会が封建制から資本主義に移行する頃、イギリスでは救貧法をつくり、働く能力はあるが働かない窮民を救済したのが制度的な始まりと言われているが、当時社会保障という言葉はなかった。
資本主義が定着していくと資本家から、失業は個人の問題であり、国による貧民救済は有害との主張がなされた。ドイツでは、防貧のために労働者が自分たちの賃金の一部を出し合って助け合う共済組合を作ったが、不況や失業による貧困が深刻すぎ全ての人を救済しきれなかった。そこで労働者は生活保障を国と資本家で行うよう主張した。結果として1883年ドイツで初めて国の制度として社会保険が実現した。社会保険制度を創設しつつ社会主義運動を弾圧する鉄血宰相オットー・フォン・ビスマルクの政策は「飴とムチ」の政策と呼ばれる。このとき保険料には、労働者だけでなく、雇用主や国の負担が導入された。このドイツの社会保険制度は、その後の福祉国家のモデルのひとつになっていく。
社会保障法
社会保障法(しゃかいほしょうほう)とは、保障の必要な者に対して、日本国 国や地方公共団体などが行う給付行政 給付行為をめぐる権利・義務を中心として、その費用負担を定めた、社会保障に関する法 (法学) 法の総称である。
広義には、公的扶助や社会保険をはじめ、環境衛生や恩給なども含む。通常は狭義に解し、社会手当や福祉 社会福祉を主要な柱としている。
社会保障に関する法としては、公的扶助関連では生活保護法や児童扶養手当法などがあり、社会保険関連では、健康保険法や国民年金法、雇用保険法など、数多くの法律がある。
アメリカ合衆国においては、1935年にニューディール政策の一環として制定されている。
社会保険制度、公的扶助、社会福祉事業の3つを骨格とし、管轄機関として社会保障局が設置されている。