スポンサードリンク
児童福祉をまるごと検索
児童福祉を詳しく調べる
児童福祉でお困りなら、ご確認してみてください。
お近くのバリアフリー(介護)リフォーム業者から
無料見積もりをお取り寄せして比較できます。
忙しいあなたにも手間なく、
ご自分の目線で、信頼の出来る工務店や
リフォーム業者をお選びいただき、
安心のリフォーム工事を行っていただければと思います。
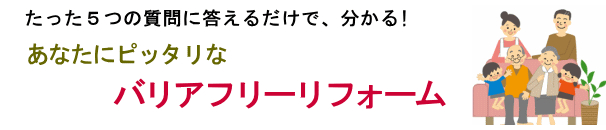
児童福祉の関連情報
児童福祉とは?
児童福祉
児童福祉(じどうふくし)とは、児童に対して行われる福祉施策のことを指す。
児童に対する福祉は、従来、障害児、孤児、母子家庭の児童に代表されるような、特別に支援を要するとされる児童に対する施策を中心に行われてきた。しかし、近年、特に日本において高齢化と同時に社会の少子化が急速に進行していることを受け、全ての家庭において児童が健全に育成されること、また、児童を生み育てやすい社会環境を整えることを主眼とした施策が中心となってきている。また、近年児童虐待の相談件数が急増しており、これへの対応も、児童福祉の大きな課題の一つである。
児童をどのように定義するかはその局面によって異なるが、児童福祉法においては、児童を「満18歳に満たないもの」と定義している。このほか、制度によっては「20歳未満のもの」「18歳に達した後最初の年度末までの間にあるもの」などと児童を定義するものもある。
児童福祉施設
児童福祉施設(しどうふくししせつ)とは、児童福祉に関する事業を行う各種の施設である。児童福祉施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)をはじめとする法令に基づいて事業を行う。児童福祉施設は、国、都道府県、市町村が設置できるほか、社会福祉法人等の者が設置することもできる。
児童福祉施設の種類は、児童福祉法の第7条に列記され、次の施設がある。
:助産施設は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする。通常、出産する者に対しては健康保険により300,000円程度の出産育児一時金が支給されるが、健康保険に加入していない生活保護受給者や、低所得者で出産に300,000円以上の費用がかかりそうな者が対象になる。通常、産婦人科を有する病院や助産院等が助産施設の指定を受けることが多い。
児童福祉司
児童福祉司(じどうふくしし)は、児童相談所に置かなければならない職員(児童福祉法第11条第1項)で、児童相談所長が定める担当区域により、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行うケースワーカー(病気や非行その他の障害等により、社会生活への適応に困難な者又は適応に失敗した者に対して社会的援助活動を行う者)の一種である(児童福祉法第11条第2項、第3項)。
児童福祉司の担当区域は、児童福祉法による保護を要する児童の数、交通事情等を考慮し、人口概ね10万人から13万人までを標準として定めることとしている(児童福祉法施行令第7条の3)。
児童福祉法
題名=児童福祉法
番号=昭和22年法律第164号
通称=なし
効力=現行法
種類=社会保障法
内容=児童福祉について
関連=なし
児童福祉法(じどうふくしほう。1947年 昭和22年〔1947年〕12月12日法律第164号)は、児童の福祉を担当する公的機関の組織や、各種施設及び事業に関する基本原則を規定した日本の法律である。社会福祉六法の1つ。
児童虐待の防止等に関する法律
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
社会福祉法
少年法
生活保護法
母子及び寡婦福祉法
労働基準法
第1章 - 総則(第1条~第18条の3)
第2章 - 福祉の保障(第19条~第34条の2)
第3章 - 事業及び施設(第34条の3~第49条)
児童福祉週間
児童福祉週間(じどうふくししゅうかん)とは、児童福祉の理念の周知を図るとともに、国民の児童に対する認識を深めるための週間。
元々は各地の福祉団体が5月初頭に「兒童福祉週間」「兒童愛護週間」などとして実施していた活動について、厚生省(当時)が児童福祉法の周知を目的として1948年(昭和23年)から「児童福祉週間」として実施したもの。毎年5月5日〜5月11日。これはこどもの日を初日とした一週間である。
期間中は児童福祉にちなんだ行事が行われるほか、一部の子ども向け施設で子どもの入場料について無料、または割引料金を適用している。
日本の週間一覧
こどもの国
5月 しとうふくししゆうかん
記念日 しとうふくししゆうかん
児童福祉 しとうふくししゆうかん
児童福祉(じどうふくし)とは、児童に対して行われる福祉施策のことを指す。
児童に対する福祉は、従来、障害児、孤児、母子家庭の児童に代表されるような、特別に支援を要するとされる児童に対する施策を中心に行われてきた。しかし、近年、特に日本において高齢化と同時に社会の少子化が急速に進行していることを受け、全ての家庭において児童が健全に育成されること、また、児童を生み育てやすい社会環境を整えることを主眼とした施策が中心となってきている。また、近年児童虐待の相談件数が急増しており、これへの対応も、児童福祉の大きな課題の一つである。
児童をどのように定義するかはその局面によって異なるが、児童福祉法においては、児童を「満18歳に満たないもの」と定義している。このほか、制度によっては「20歳未満のもの」「18歳に達した後最初の年度末までの間にあるもの」などと児童を定義するものもある。
児童福祉施設
児童福祉施設(しどうふくししせつ)とは、児童福祉に関する事業を行う各種の施設である。児童福祉施設は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)をはじめとする法令に基づいて事業を行う。児童福祉施設は、国、都道府県、市町村が設置できるほか、社会福祉法人等の者が設置することもできる。
児童福祉施設の種類は、児童福祉法の第7条に列記され、次の施設がある。
:助産施設は、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする。通常、出産する者に対しては健康保険により300,000円程度の出産育児一時金が支給されるが、健康保険に加入していない生活保護受給者や、低所得者で出産に300,000円以上の費用がかかりそうな者が対象になる。通常、産婦人科を有する病院や助産院等が助産施設の指定を受けることが多い。
児童福祉司
児童福祉司(じどうふくしし)は、児童相談所に置かなければならない職員(児童福祉法第11条第1項)で、児童相談所長が定める担当区域により、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行うケースワーカー(病気や非行その他の障害等により、社会生活への適応に困難な者又は適応に失敗した者に対して社会的援助活動を行う者)の一種である(児童福祉法第11条第2項、第3項)。
児童福祉司の担当区域は、児童福祉法による保護を要する児童の数、交通事情等を考慮し、人口概ね10万人から13万人までを標準として定めることとしている(児童福祉法施行令第7条の3)。
児童福祉法
題名=児童福祉法
番号=昭和22年法律第164号
通称=なし
効力=現行法
種類=社会保障法
内容=児童福祉について
関連=なし
児童福祉法(じどうふくしほう。1947年 昭和22年〔1947年〕12月12日法律第164号)は、児童の福祉を担当する公的機関の組織や、各種施設及び事業に関する基本原則を規定した日本の法律である。社会福祉六法の1つ。
児童虐待の防止等に関する法律
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
社会福祉法
少年法
生活保護法
母子及び寡婦福祉法
労働基準法
第1章 - 総則(第1条~第18条の3)
第2章 - 福祉の保障(第19条~第34条の2)
第3章 - 事業及び施設(第34条の3~第49条)
児童福祉週間
児童福祉週間(じどうふくししゅうかん)とは、児童福祉の理念の周知を図るとともに、国民の児童に対する認識を深めるための週間。
元々は各地の福祉団体が5月初頭に「兒童福祉週間」「兒童愛護週間」などとして実施していた活動について、厚生省(当時)が児童福祉法の周知を目的として1948年(昭和23年)から「児童福祉週間」として実施したもの。毎年5月5日〜5月11日。これはこどもの日を初日とした一週間である。
期間中は児童福祉にちなんだ行事が行われるほか、一部の子ども向け施設で子どもの入場料について無料、または割引料金を適用している。
日本の週間一覧
こどもの国
5月 しとうふくししゆうかん
記念日 しとうふくししゆうかん
児童福祉 しとうふくししゆうかん