スポンサードリンク
保険をまるごと検索
保険を詳しく調べる
保険でお困りなら、ご確認してみてください。
お近くのバリアフリー(介護)リフォーム業者から
無料見積もりをお取り寄せして比較できます。
忙しいあなたにも手間なく、
ご自分の目線で、信頼の出来る工務店や
リフォーム業者をお選びいただき、
安心のリフォーム工事を行っていただければと思います。
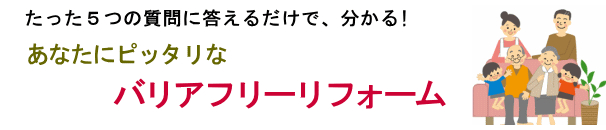
保険の関連情報
保険とは?
保険
保険(ほけん)は、偶然に発生する事故(保険事故)によって生じる財産上の損失に備えて、多数の者が金銭(保険料)を出し合い、その資金によって事故が発生した者に金銭(保険金)を給付する制度。以下では主に日本における保険(私保険)について記述する。
保険関係の設定を目的とする契約を保険契約といい、保険契約の当事者として、保険料の支払義務を負う者を保険契約者、保険事故が発生した場合に保険金を支払うことを引き受ける者を保険者というなお、被保険者の意味は、生命保険と損害保険、社会保険によってそれぞれ異なる。生命保険ではその者の生死が保険事故となるされている人を被保険者といい、損害保険では保険事故発生のとき保険金の支払を受ける権利を持つ者を被保険者という。社会保険では、保険料の支払義務を負担するとともに、保険事故が発生したときは、保険給付を受給する者を被保険者という。詳しくは、被保険者または各保険の項目を参照のこと。。2010年4月1日に施行される保険法では、保険契約について「保険契約、共済契約その他いかなる名称であるかを問わず、当事者の一方が一定の事由が生じたことを条件として財産上の給付(生命保険契約及び傷害疾病定額保険契約にあっては、金銭の支払に限る。以下「保険給付」という)を行うことを約し、相手方がこれに対して当該一定の事由の発生の可能性に応じたものとして保険料(共済掛金を含む。以下同じ)を支払うことを約する契約をいう。」と定義している。保険者として保険事業(保険業)を営む会社を保険会社といい、日本では保険業法(平成7年法律第105号)により規制されている。なお、保険に関する法分野を研究する学問、および保険に関する法令を総称して広義の意味での保険法という。現在の日本では、保険に関しては商法(第2編第10章)等に定められており、保険法という名の法律はなかったが、商法の規定に今日的見直しを行った保険法が2008年5月30日に成立、同年6月6日に公布された(平成20年法律第56号)。
保険会社
『保険』より : 保険(ほけん)とは、加入者の財産や生命、健康などの危険(事件、事故や災害など)に対し、金銭面での損失をカバーするための事業である。
加入者数が充分大きければ危険率は一定の経験値に収束する、という大数の法則により、危険率に見合った保険料を徴収すれば収支が均衡するはずである、という考え方に基いている。
日本では、国が直接または間接にかかわる社会保険として健康保険や介護保険、労働保険(雇用保険、労災保険)、年金保険(厚生年金・国民年金など)の制度があり、医療費や介護費、失業時の生活費がカバーされ、また老後の生活支援の一部となっている。
また、日本郵政公社(旧郵政事業庁)による、簡易保険(加入条件が緩やか)がある。
保険業法
保険業法 (ほけんぎょうほう - 公布:平成7年(1995年)6月7日法律第105号、施行:平成8年(1996年)4月1日) とは、保険業の公共性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする(同法第1編第1条)法律である。
同法は保険監督法の基本法として、保険会社および保険募集に対する監督に係るあらゆる事項について規定しており、組織に関し保険会社の特性に照らして会社法に修正を行う部分、業務を規制し、監督の実効性を担保する部分、保険募集規制し、消費者保護を目的とする部分からなる。
保険金不払い事件
保険金不払い事件(ほけんきんふばらいじけん)または保険金不払い問題(ほけんきんふばらいもんだい)とは、2005年(平成17年)2月20日に発覚した明治安田生命保険による死亡保険金の不当な不払いを発端とした、数多くの保険会社(生命保険会社、損害保険会社問わず)が起こした、保険金を支払わなければならない事案や事故に対して正当な理由無く保険金を支払わずにいた事件。1つの保険会社だけならず、数多くの保険会社がこのような保険金の不当な不払いを行っていたことから、保険業界全体の著しい腐敗が明らかになり、社会問題にまで発展した。
その特徴から、一部からは保険会社による保険金詐欺とまで比喩される。
保険金不払い問題
『保険金不払い事件』より : 保険金不払い事件(ほけんきんふばらいじけん)または保険金不払い問題(ほけんきんふばらいもんだい)とは、2005年(平成17年)2月20日に発覚した明治安田生命保険による死亡保険金の不当な不払いを発端とした、数多くの保険会社(生命保険会社、損害保険会社問わず)が起こした、保険金を支払わなければならない事案や事故に対して正当な理由無く保険金を支払わずにいた事件。1つの保険会社だけならず、数多くの保険会社がこのような保険金の不当な不払いを行っていたことから、保険業界全体の著しい腐敗が明らかになり、社会問題にまで発展した。
その特徴から、一部からは保険会社による保険金詐欺とまで比喩される。
保険持株会社
『金融持株会社』より : 金融持株会社(きんゆうもちかぶがいしゃ)とは、持株会社の内、子会社とする会社の大半が金融に関する事業を行うものである。1998年の独占禁止法改正により設立が解禁された。
日本では、法律によって設立に認可を受けなければならないものがある。例えば、銀行を子会社とするものや保険会社を子会社とするものの場合は、前者は銀行法、後者は保険業法に基づいて内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
一方、証券会社の場合は、他の法人その他の団体が、持株会社に該当し、又は該当しないこととなった場合に、証券取引法第五十四条第一項第八号及び証券会社に関する内閣府令第四十六条第一項第四号の二に基づいて当該証券会社は遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
保険法
題名=保険法
通称=保険法
番号=平成20年法律第56号
効力=未施行
種類=商法、金融法
内容=保険に係る契約の成立、効力、履行及び終了
関連=保険業法
保険法(ほけんほう)とは、保険に関して規定・規制する法律をいう。日本では、従来「保険法」と題する法律は存在せず、商法の商行為法の一部を構成する第2編「商行為」第10章「保険」(陸上保険)および第3編「海商」第6章「保険」(海上保険)を総称して保険法と呼んできた。しかし、保険法の口語化・現代化を目指した検討が法務省法制審議会の保険法部会で行われた結果、商法から独立した単行法としての保険法が立法されることになり、2008年5月30日に保険法が成立した。
この法律では、従来規定が存在しなかった、人の疾病や災害に際して給付を行う、いわゆる第三分野保険保険(保険法中では「傷害疾病損害保険」および「傷害疾病定額保険」)に関する規定の新設や、自発的報告義務とされてきた告知義務を質問回答義務に緩和するなどの改正がなされており、2010年4月1日施行の予定。なお、海上保険に関する規定は従来どおり商法第3編「海商」中に規定が残る。
保険事故
保険事故(ほけんじこ)とは、保険において保険者の保険金支払義務を具体化させる事故、つまり、当該事故が発生したときに保険者が保険金の支払をしなければならない事実をいう。偶然なものでなければならないが、いつか必ず発生するといったものでもよい。
例示すると、生命保険の場合は人の死亡、火災保険の場合は火災による建物等の焼失、損害賠償責任保険の場合は一定の事由による損害賠償責任の発生などが保険事故に当たる。
特殊な例として、預金保険においては「金融機関の預金等の払戻しの停止」および「金融機関の営業免許の取消し、破産手続開始の決定又は解散の決議」を保険事故と定義している(預金保険法第49条第2項)。
保険 *ほけん
保険薬局
保険薬局(ほけんやっきょく)とは薬剤師が健康保険を使い調剤を行っていたり(保険調剤)、大衆薬の販売を行っている薬局のことである。
保険薬局と「薬局」の一種である薬局との大きな違いは、保険薬局が処方せんの受付(保険調剤)を行うことができるという点である。「薬局」の一種である薬局では大衆薬の販売や調剤を行うことはできるが、処方せんを受け付ける(保険調剤)ことはできない。
また多くの場合、保険薬局には「保険薬局」、「保険調剤薬局」、「処方せん受付」、「基準薬局」などの表示がある。
医療 ほけんやつきよく
薬剤師 ほけんやつきよく
保険計理人
保険計理人(ほけんけいりにん)とは、保険計理の専門家である。
保険計理人は、次の4つの要件を満たし厚生労働大臣の認可を受けたものである。
日本アクチェアリー会の正会員であること
保険計理の実務に5年以上の経験があること
第1次試験の全科目に合格し、保険数理の実務に10年以上の経験があること
十分な社会的信用を有するものであること
信託銀行
アクチュアリー
保険 ほけんけいりにん
国家資格 ほけんけいりにん
保険(ほけん)は、偶然に発生する事故(保険事故)によって生じる財産上の損失に備えて、多数の者が金銭(保険料)を出し合い、その資金によって事故が発生した者に金銭(保険金)を給付する制度。以下では主に日本における保険(私保険)について記述する。
保険関係の設定を目的とする契約を保険契約といい、保険契約の当事者として、保険料の支払義務を負う者を保険契約者、保険事故が発生した場合に保険金を支払うことを引き受ける者を保険者というなお、被保険者の意味は、生命保険と損害保険、社会保険によってそれぞれ異なる。生命保険ではその者の生死が保険事故となるされている人を被保険者といい、損害保険では保険事故発生のとき保険金の支払を受ける権利を持つ者を被保険者という。社会保険では、保険料の支払義務を負担するとともに、保険事故が発生したときは、保険給付を受給する者を被保険者という。詳しくは、被保険者または各保険の項目を参照のこと。。2010年4月1日に施行される保険法では、保険契約について「保険契約、共済契約その他いかなる名称であるかを問わず、当事者の一方が一定の事由が生じたことを条件として財産上の給付(生命保険契約及び傷害疾病定額保険契約にあっては、金銭の支払に限る。以下「保険給付」という)を行うことを約し、相手方がこれに対して当該一定の事由の発生の可能性に応じたものとして保険料(共済掛金を含む。以下同じ)を支払うことを約する契約をいう。」と定義している。保険者として保険事業(保険業)を営む会社を保険会社といい、日本では保険業法(平成7年法律第105号)により規制されている。なお、保険に関する法分野を研究する学問、および保険に関する法令を総称して広義の意味での保険法という。現在の日本では、保険に関しては商法(第2編第10章)等に定められており、保険法という名の法律はなかったが、商法の規定に今日的見直しを行った保険法が2008年5月30日に成立、同年6月6日に公布された(平成20年法律第56号)。
保険会社
『保険』より : 保険(ほけん)とは、加入者の財産や生命、健康などの危険(事件、事故や災害など)に対し、金銭面での損失をカバーするための事業である。
加入者数が充分大きければ危険率は一定の経験値に収束する、という大数の法則により、危険率に見合った保険料を徴収すれば収支が均衡するはずである、という考え方に基いている。
日本では、国が直接または間接にかかわる社会保険として健康保険や介護保険、労働保険(雇用保険、労災保険)、年金保険(厚生年金・国民年金など)の制度があり、医療費や介護費、失業時の生活費がカバーされ、また老後の生活支援の一部となっている。
また、日本郵政公社(旧郵政事業庁)による、簡易保険(加入条件が緩やか)がある。
保険業法
保険業法 (ほけんぎょうほう - 公布:平成7年(1995年)6月7日法律第105号、施行:平成8年(1996年)4月1日) とは、保険業の公共性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする(同法第1編第1条)法律である。
同法は保険監督法の基本法として、保険会社および保険募集に対する監督に係るあらゆる事項について規定しており、組織に関し保険会社の特性に照らして会社法に修正を行う部分、業務を規制し、監督の実効性を担保する部分、保険募集規制し、消費者保護を目的とする部分からなる。
保険金不払い事件
保険金不払い事件(ほけんきんふばらいじけん)または保険金不払い問題(ほけんきんふばらいもんだい)とは、2005年(平成17年)2月20日に発覚した明治安田生命保険による死亡保険金の不当な不払いを発端とした、数多くの保険会社(生命保険会社、損害保険会社問わず)が起こした、保険金を支払わなければならない事案や事故に対して正当な理由無く保険金を支払わずにいた事件。1つの保険会社だけならず、数多くの保険会社がこのような保険金の不当な不払いを行っていたことから、保険業界全体の著しい腐敗が明らかになり、社会問題にまで発展した。
その特徴から、一部からは保険会社による保険金詐欺とまで比喩される。
保険金不払い問題
『保険金不払い事件』より : 保険金不払い事件(ほけんきんふばらいじけん)または保険金不払い問題(ほけんきんふばらいもんだい)とは、2005年(平成17年)2月20日に発覚した明治安田生命保険による死亡保険金の不当な不払いを発端とした、数多くの保険会社(生命保険会社、損害保険会社問わず)が起こした、保険金を支払わなければならない事案や事故に対して正当な理由無く保険金を支払わずにいた事件。1つの保険会社だけならず、数多くの保険会社がこのような保険金の不当な不払いを行っていたことから、保険業界全体の著しい腐敗が明らかになり、社会問題にまで発展した。
その特徴から、一部からは保険会社による保険金詐欺とまで比喩される。
保険持株会社
『金融持株会社』より : 金融持株会社(きんゆうもちかぶがいしゃ)とは、持株会社の内、子会社とする会社の大半が金融に関する事業を行うものである。1998年の独占禁止法改正により設立が解禁された。
日本では、法律によって設立に認可を受けなければならないものがある。例えば、銀行を子会社とするものや保険会社を子会社とするものの場合は、前者は銀行法、後者は保険業法に基づいて内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
一方、証券会社の場合は、他の法人その他の団体が、持株会社に該当し、又は該当しないこととなった場合に、証券取引法第五十四条第一項第八号及び証券会社に関する内閣府令第四十六条第一項第四号の二に基づいて当該証券会社は遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
保険法
題名=保険法
通称=保険法
番号=平成20年法律第56号
効力=未施行
種類=商法、金融法
内容=保険に係る契約の成立、効力、履行及び終了
関連=保険業法
保険法(ほけんほう)とは、保険に関して規定・規制する法律をいう。日本では、従来「保険法」と題する法律は存在せず、商法の商行為法の一部を構成する第2編「商行為」第10章「保険」(陸上保険)および第3編「海商」第6章「保険」(海上保険)を総称して保険法と呼んできた。しかし、保険法の口語化・現代化を目指した検討が法務省法制審議会の保険法部会で行われた結果、商法から独立した単行法としての保険法が立法されることになり、2008年5月30日に保険法が成立した。
この法律では、従来規定が存在しなかった、人の疾病や災害に際して給付を行う、いわゆる第三分野保険保険(保険法中では「傷害疾病損害保険」および「傷害疾病定額保険」)に関する規定の新設や、自発的報告義務とされてきた告知義務を質問回答義務に緩和するなどの改正がなされており、2010年4月1日施行の予定。なお、海上保険に関する規定は従来どおり商法第3編「海商」中に規定が残る。
保険事故
保険事故(ほけんじこ)とは、保険において保険者の保険金支払義務を具体化させる事故、つまり、当該事故が発生したときに保険者が保険金の支払をしなければならない事実をいう。偶然なものでなければならないが、いつか必ず発生するといったものでもよい。
例示すると、生命保険の場合は人の死亡、火災保険の場合は火災による建物等の焼失、損害賠償責任保険の場合は一定の事由による損害賠償責任の発生などが保険事故に当たる。
特殊な例として、預金保険においては「金融機関の預金等の払戻しの停止」および「金融機関の営業免許の取消し、破産手続開始の決定又は解散の決議」を保険事故と定義している(預金保険法第49条第2項)。
保険 *ほけん
保険薬局
保険薬局(ほけんやっきょく)とは薬剤師が健康保険を使い調剤を行っていたり(保険調剤)、大衆薬の販売を行っている薬局のことである。
保険薬局と「薬局」の一種である薬局との大きな違いは、保険薬局が処方せんの受付(保険調剤)を行うことができるという点である。「薬局」の一種である薬局では大衆薬の販売や調剤を行うことはできるが、処方せんを受け付ける(保険調剤)ことはできない。
また多くの場合、保険薬局には「保険薬局」、「保険調剤薬局」、「処方せん受付」、「基準薬局」などの表示がある。
医療 ほけんやつきよく
薬剤師 ほけんやつきよく
保険計理人
保険計理人(ほけんけいりにん)とは、保険計理の専門家である。
保険計理人は、次の4つの要件を満たし厚生労働大臣の認可を受けたものである。
日本アクチェアリー会の正会員であること
保険計理の実務に5年以上の経験があること
第1次試験の全科目に合格し、保険数理の実務に10年以上の経験があること
十分な社会的信用を有するものであること
信託銀行
アクチュアリー
保険 ほけんけいりにん
国家資格 ほけんけいりにん