スポンサードリンク
身体障害をまるごと検索
身体障害を詳しく調べる
身体障害でお困りなら、ご確認してみてください。
お近くのバリアフリー(介護)リフォーム業者から
無料見積もりをお取り寄せして比較できます。
忙しいあなたにも手間なく、
ご自分の目線で、信頼の出来る工務店や
リフォーム業者をお選びいただき、
安心のリフォーム工事を行っていただければと思います。
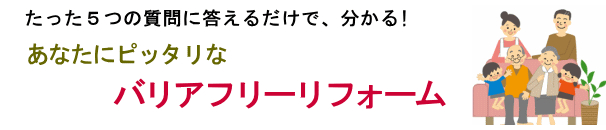
身体障害の関連情報
身体障害とは?
身体障害
身体障害(しんたいしょうがい)とは、一般的には先天的あるいは後天的な理由で、身体機能の一部にリハビリテーション#障害の医療モデル 障害を生じている状態。
手・足がない、機能しないなどの肢体不自由、脳内の障害により正常に手足が動かない脳性麻痺などの種類がある。視覚障害、聴覚障害、心臓病なども広義の身体障害である。
先天的に身体障害を持つ場合、まれに知的障害を併せ持つことがあり、これを重複障害という。また複数の部位に身体障害を持つことを指すこともある。
身体障害者福祉法の対象となる障害は、視覚障害、聴覚障害・平衡機能障害、音声・言語障害(そしゃく障害を含む)、肢体不自由、心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・大腸・小腸・免疫等の内部障害の6種類に大別される。例えば脳梗塞で倒れた人の場合、脳梗塞の後遺症によって生じた肢体不自由は同法で支援の対象となるが、併せて記憶障害などが発生しても、それ自体は身体障害として認定されない。痴呆 認知症など、精神障害を合併した場合は精神保健福祉法による援助の対象となる。
身体障害者
『身体障害』より : 身体障害(しんたいしょうがい)とは、一般的には先天的あるいは後天的な理由で、身体機能の一部にリハビリテーション#障害の医療モデル 障害を生じている状態。
手・足がない、機能しないなどの肢体不自由、脳内の障害により正常に手足が動かない脳性麻痺などの種類がある。視覚障害、聴覚障害、心臓病なども広義の身体障害である。
先天的に身体障害を持つ場合、まれに知的障害を併せ持つことがあり、これを重複障害という。また複数の部位に身体障害を持つことを指すこともある。
身体障害者福祉法の対象となる障害は、視覚障害、聴覚障害・平衡機能障害、音声・言語障害(そしゃく障害を含む)、肢体不自由、心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・大腸・小腸・免疫等の内部障害の6種類に大別される。例えば脳梗塞で倒れた人の場合、脳梗塞の後遺症によって生じた肢体不自由は同法で支援の対象となるが、併せて記憶障害などが発生しても、それ自体は身体障害として認定されない。痴呆 認知症など、精神障害を合併した場合は精神保健福祉法による援助の対象となる。
身体障害者補助犬法
身体障害者補助犬法(しんたいしょうがいしゃほじょけんほう;2002年 平成14年5月29日法律第49号)は、身体障害者補助犬を使う身体障害者が自立と社会参加することが促進されるための法律。
同法第1条に拠れば
:身体障害者補助犬を訓練する事業を行う者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者の義務等を定めるとともに、身体障害者が国等が管理する施設、公共交通機関等を利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することができるようにするための措置を講ずること等により、身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図り、もって身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与することを目的とする
身体障害者手帳
身体障害者手帳(しんたいしょうがいしゃてちょう)とは身体障害者が健常者と同等の生活を送るために最低限必要な援助を受けるための、いわば証明書にあたる。
援助内容は補装具・義肢の交付など有形のものから、ヘルパーサービスなど無形のものまで多岐にわたる。
等級は数字であらわされ、数字が小さいほど重度である。
障害の種類は、視覚障害、聴覚障害、音声・言語機能障害、そしゃく機能障害、肢体不自由、内部障害である心臓機能障害、
呼吸器機能障害、じん臓機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、計11種類である。
最高度は1級。障害を複数もつ場合は、各部位に対して個別に等級がつき、その合計で手帳等級が決定される。
身体障害者福祉法
題名=身体障害者福祉法
番号=昭和24年法律第283号
通称=なし
効力=現行法
種類=社会保障法
内容=身体障害者の福祉について
関連=
身体障害者福祉法
身体障害者福祉司
第1条 この法律は、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条 すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。
2 すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。
身体障害者標識
身体障害者標識(しんたいしょうがいしゃひょうしき)とは、道路交通法に基づく標識の一つ。円形をしており、青地に白の四葉の植物をあしらった図案で、一般的には四葉マーク(よつばマーク)やクローバーマークの通称で呼ばれる。
2001年(平成13年)の道路交通法改正による障害者に係る免許の欠格事由の見直しに伴い導入された。
肢体不自由であることを理由に当該免許に条件を付されているものは、当該肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、運転する車両の前後の視認性の高い部分(地上0.4〜1.2m以内)に掲示して運転するように務めなければならない。
また、初心者マークと同様に、周囲の運転者はこの標識を掲示した車両を保護する義務を有し、幅寄せ・割り込みなどの行為を行なってはならないと定められており、表示車に対して幅寄せ・割り込みをした場合は交通違反となる(詳細は割り込み (運転)を参照)。
身体障害者補助犬
身体障害者補助犬 (しんたいしょうがいしゃほじょけん)、アシスタントドッグ (Assistance Dog) は、人を助けるイヌ、特に身体障害者補助犬法で規定された、
盲導犬 - 視覚障害者の手助けをする
聴導犬 - 聴覚障害者の手助けをする
介助犬 - 運動機能に障害がある人の手助けをする
をいう。詳細については各項目を参照されたい。
身体障害者補助犬法
紙ふうせん - 身体障害者補助犬法施行応援歌『補助犬トリオ』を自作自演している。
犬 しんたいしようかいしやほしよけん
障害者 しんたいしようかいしやほしよけん
身体障害(しんたいしょうがい)とは、一般的には先天的あるいは後天的な理由で、身体機能の一部にリハビリテーション#障害の医療モデル 障害を生じている状態。
手・足がない、機能しないなどの肢体不自由、脳内の障害により正常に手足が動かない脳性麻痺などの種類がある。視覚障害、聴覚障害、心臓病なども広義の身体障害である。
先天的に身体障害を持つ場合、まれに知的障害を併せ持つことがあり、これを重複障害という。また複数の部位に身体障害を持つことを指すこともある。
身体障害者福祉法の対象となる障害は、視覚障害、聴覚障害・平衡機能障害、音声・言語障害(そしゃく障害を含む)、肢体不自由、心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・大腸・小腸・免疫等の内部障害の6種類に大別される。例えば脳梗塞で倒れた人の場合、脳梗塞の後遺症によって生じた肢体不自由は同法で支援の対象となるが、併せて記憶障害などが発生しても、それ自体は身体障害として認定されない。痴呆 認知症など、精神障害を合併した場合は精神保健福祉法による援助の対象となる。
身体障害者
『身体障害』より : 身体障害(しんたいしょうがい)とは、一般的には先天的あるいは後天的な理由で、身体機能の一部にリハビリテーション#障害の医療モデル 障害を生じている状態。
手・足がない、機能しないなどの肢体不自由、脳内の障害により正常に手足が動かない脳性麻痺などの種類がある。視覚障害、聴覚障害、心臓病なども広義の身体障害である。
先天的に身体障害を持つ場合、まれに知的障害を併せ持つことがあり、これを重複障害という。また複数の部位に身体障害を持つことを指すこともある。
身体障害者福祉法の対象となる障害は、視覚障害、聴覚障害・平衡機能障害、音声・言語障害(そしゃく障害を含む)、肢体不自由、心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・大腸・小腸・免疫等の内部障害の6種類に大別される。例えば脳梗塞で倒れた人の場合、脳梗塞の後遺症によって生じた肢体不自由は同法で支援の対象となるが、併せて記憶障害などが発生しても、それ自体は身体障害として認定されない。痴呆 認知症など、精神障害を合併した場合は精神保健福祉法による援助の対象となる。
身体障害者補助犬法
身体障害者補助犬法(しんたいしょうがいしゃほじょけんほう;2002年 平成14年5月29日法律第49号)は、身体障害者補助犬を使う身体障害者が自立と社会参加することが促進されるための法律。
同法第1条に拠れば
:身体障害者補助犬を訓練する事業を行う者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者の義務等を定めるとともに、身体障害者が国等が管理する施設、公共交通機関等を利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することができるようにするための措置を講ずること等により、身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図り、もって身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与することを目的とする
身体障害者手帳
身体障害者手帳(しんたいしょうがいしゃてちょう)とは身体障害者が健常者と同等の生活を送るために最低限必要な援助を受けるための、いわば証明書にあたる。
援助内容は補装具・義肢の交付など有形のものから、ヘルパーサービスなど無形のものまで多岐にわたる。
等級は数字であらわされ、数字が小さいほど重度である。
障害の種類は、視覚障害、聴覚障害、音声・言語機能障害、そしゃく機能障害、肢体不自由、内部障害である心臓機能障害、
呼吸器機能障害、じん臓機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、計11種類である。
最高度は1級。障害を複数もつ場合は、各部位に対して個別に等級がつき、その合計で手帳等級が決定される。
身体障害者福祉法
題名=身体障害者福祉法
番号=昭和24年法律第283号
通称=なし
効力=現行法
種類=社会保障法
内容=身体障害者の福祉について
関連=
身体障害者福祉法
身体障害者福祉司
第1条 この法律は、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条 すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努めなければならない。
2 すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。
身体障害者標識
身体障害者標識(しんたいしょうがいしゃひょうしき)とは、道路交通法に基づく標識の一つ。円形をしており、青地に白の四葉の植物をあしらった図案で、一般的には四葉マーク(よつばマーク)やクローバーマークの通称で呼ばれる。
2001年(平成13年)の道路交通法改正による障害者に係る免許の欠格事由の見直しに伴い導入された。
肢体不自由であることを理由に当該免許に条件を付されているものは、当該肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、運転する車両の前後の視認性の高い部分(地上0.4〜1.2m以内)に掲示して運転するように務めなければならない。
また、初心者マークと同様に、周囲の運転者はこの標識を掲示した車両を保護する義務を有し、幅寄せ・割り込みなどの行為を行なってはならないと定められており、表示車に対して幅寄せ・割り込みをした場合は交通違反となる(詳細は割り込み (運転)を参照)。
身体障害者補助犬
身体障害者補助犬 (しんたいしょうがいしゃほじょけん)、アシスタントドッグ (Assistance Dog) は、人を助けるイヌ、特に身体障害者補助犬法で規定された、
盲導犬 - 視覚障害者の手助けをする
聴導犬 - 聴覚障害者の手助けをする
介助犬 - 運動機能に障害がある人の手助けをする
をいう。詳細については各項目を参照されたい。
身体障害者補助犬法
紙ふうせん - 身体障害者補助犬法施行応援歌『補助犬トリオ』を自作自演している。
犬 しんたいしようかいしやほしよけん
障害者 しんたいしようかいしやほしよけん